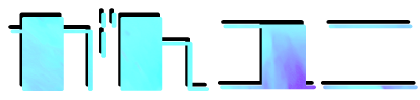11|15
懐古的なことを書く。
いまから20年くらい前の病理診断レポートは、手書きであった。臨床医は依頼内容(どういう患者であるか、細胞を取った場所はどこか、主治医はなんの病気だと考えているか)を、かんたんなイラストや模式図などを添えて、ボールペンで書く。同じ紙の下半分には、「病理診断」と冠された白枠があって、病理医はここに思いの丈をボールペンで書く。
レポートは複写式になっていて、感圧で青字まみれになった二枚目のほうは検査室で保管し、一枚目の迫力ある生字の見やすいほうを臨床医に返す。
昔はそうだった。私も微妙にこの時代を覚えている。
その後、急速にPCが導入され、乱文・乱筆の類が一掃された(病理医はたいてい字がきれいだったが中にはとんでもない悪筆も混じっていた)。そしてレポートの作成速度がとても早くなった。コピペが可能になったことがでかい。「癌取扱い規約」のたぐいは、胃癌、大腸癌、乳癌など、癌ごとに決められたチェックリストがあって、それらを毎回埋めていく必要があるのだが、手書きでこのような項目をいちいち書くのに比べて、PCでひながたをコピペできるというのは本当に格段に楽である。
加えて見逃せないのは検索機能が加わったことだ。デジタルレポートは、書き終わって診断登録した瞬間からすぐに検索対象となる。これにより、病理診断が病理医はもちろんのことあらゆる医療者にとって非常に活用しやすくなった。
いいことばかりだ。
では、かつての病理医たちがみな、レポートのデジタル化を喜んだかというと、みなさんの予想通り、必ずしもそういうわけでもなかった。
かつての病理医たちは、「手書きゆえの強調のしかた」を大事にしていた。絶対に読んでほしい部分をちょっと大きめに書くとか、下線を引くとか、色を変えるとか、レポートが2枚目に突入しないようにコンパクトにまとめて書くといった、アナログのフレキシビリティを存分に活用して、彼らは病理診断を書いていた。「絵日記」的な病理診断には独特の味わいがあったし、「和歌が書かれたサイン色紙」のような風格ある病理診断を見ることもしばしばであったし、「文豪からの一筆箋」といった佇まいの病理診断が真理の扉を開く機会に遭遇して私たちは震えたものである。
そういったものは、病理診断支援ソフトの導入で、ほぼ絶滅した。インデントや行の幅を調整することがむずかしいし、筆圧の表現はなおさらである。注釈の付け方にも味わいはなくなった。
もっとも、アナログのレポートが駆逐されたことを懐かしく悲しむのは病理医ばかりだ。いちばん大事な受け取り手である臨床医から、「あの時代のレポートは良かったなあ」などと不満を聞いたことはない。病理診断科の技術の進歩に茶々をいれないようにしてくれている可能性もないではないが、やっぱり、受け取るほうからしたら、デジタル化されたレポートのほうが何倍もよいものなのだろう。懐古趣味もたいがいにしたほうがいい。こういう話は、あまり、多くの人の目に触れる場所には書かないほうがいいだろう(笑)。