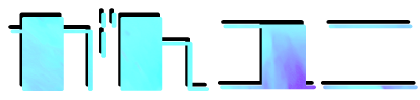0|0
指定された場所は川沿いのビルだった。ベビーカー連れの親子が日差しの中を歩いている。アポイントメントより少し前に近隣の中華料理屋に入って、小籠包ランチを食べ、食後にお手洗いで歯を磨いていると、幼稚園くらいの男の子ふたりが若い父親といっしょに用を足しに入ってきて、私の隣の洗面台で入念に手を洗い、鏡を見てふりふりと踊って爆発するように駆け抜けていった。
今日はがんユニの取材。受けるほうではない。インタビューするほう。
一人目への取材をしたのがちょうど一年前のことだった。最近ようやくペースアップできている。来月にもうひとり、三か月後にもうひとりお話しをうかがう予定である。そこまで終わるとちょうど半分くらい。見切り発車したつもりはなかったが、いまのところ、私たちの列車は思いのほかたくさんの風景の中を走っている。
この企画がスタートしたとき、私は担当の編集者に、「二年くらいかかると思います」と告げた。ややふっかけ気味に告げた数字だったが、思えばいいセンだ。インタビューが終わるまであと一年、それをまとめるのにさらに半年……都合二年半といったところだろう。
三十分前。近隣のカフェで編集者と落ち合って打ち合わせ。
学生が試験勉強をしている。PCになにやら打ち込んでいるのはライターだろうか。動画を収録している三人組。本を読んでいる人がいないことに慣れてしまった。いや、この中のひとり、ふたりはスマホで電子書籍を読んでいるかもしれないのだけれど。
―――あの先生へのインタビューはご快諾いただけました。あちらの先生は自分では務まらないとのことでご辞退されました。あの先生にはそろそろメールでご予定をおうかがいしましょう。あの先生からはメールのお返事がいただけないのですが―――
時間。
やってきた医者。
私が内に抱えている「精神科医」の爬虫類的なイメージとは違う。恒温み。熱が逃げていかないための仕組み。
カメラマンが「外で写真を撮りましょう」と言った。少し肌寒いが光量が多い。編集者はレフ板をもたされている。がんばってくださいと告げると笑っている。清水研先生も笑っている。にこやかな方だなあと感じた。
がん研有明病院・腫瘍精神科部長。直接お目にかかるのははじめてだ。しかし、インタビューを進めるうち、私は彼の研究歴を、なぜかすでに知っているということに気づいた。インタビューの最中にはそれがなぜだかわからなかった。どこかで誰かの語った話を聞いたことがあったのだろうかと思った。しかし、帰りの飛行機の中で思い出した。
『Cancer board square』。もう休刊してしまったがいい雑誌だった。そのなかに「がん患者と向き合う精神科医」として連載をもたれていたのが清水先生だった。もう六年くらい前に読んだ記事だ。詳しいところは覚えていない。そのときの「がんと精神科」の距離感というか、温度感のようなものを、私はまだ持っていた。
文字や音声による情報ではなく、温痛覚的なもので、私は清水先生の語りと「再開」した。それは偶然だった。私ががんユニのインタビュイーとして清水先生を推薦したのには違う縁がいくつかあったからで、決して私がかつてCancer board squareの記事を読んだからというわけではなかった。しかし、結果的に、それは蓋然的であるように見えた。
編集者が言った。企画の色味がぐっと変わってきましたね。私は答えた。そうですか。いや、これはもともとこういう企画だったんですよ。自分が少し反発していることに自分でも驚いた。
清水先生の眼差すものの話はとてもおもしろかった。彼はいわゆる「第一人者」であるが、第一の人という意味だけではなく、つねに一人の者でもあるのかもしれなかった。専門病院の中で、がんという病気によってつらさやしんどさを感じる患者と向き合うにあたり、科学のできることがどこまであるのかと丁寧に間合いをはかりながら、非線形の複雑性に半身をひたすように「役に立っていく」清水先生の話を、私は過剰に相槌をうちながら聞いた。インタビュアーなのに、カウンセリングを受けているような気持ちになった。それは清水先生が精神科医だったから、であろうか。どうもそういうわけでもないような気がした。
さまざまな角度からがんを眼差す方々に話を聞くことは、こと、私にとって、極めてカウンセリング的な行為なのだということを、近頃は確信している。