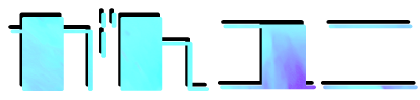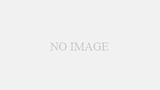0|0
羽田空港から柏駅行のリムジンに乗ればいい。冷たい雨の降りしきる春の首都高で、私はルル・ミラーの自己主張のやたらと強い著作を読みながら、微弱な緊張と戦っていた。柏のインターチェンジでバスが減速するころには、スタンフォード大学初代学長のエピソードに対する興味は一切失われていた。
40分後に始まる。ついにこの日が来た。インタビュー。12人目。
「抗がん剤」を使う医者。
少し遡る。
2022年12月2日、私は、外科医・山本健人(現・京都大学消化器外科)といっしょに、ウェブ企画に登壇した。感染症禍に一定の方向性が見え始めたタイミングで、私たちは尾身茂先生にお話をうかがった。
すごい夜だった。はっとするような話でもあり、しみいるような話でもあり、視野の広さと情念の深さとが長時間うねりながら維持されていて、この方は四次元の各領域に張り巡らせた専門性と矜持の総量が半端ないな、ということを、ずっと感じていた。
会が終わり、尾身先生がお帰りになったあと、私は山本に告げた。
「なんか、もう、『これ以上』ってないかも」
「これ以上、ですか?」
「今後、どれだけの『大物』と会っても緊張しないよね」
「なるほど、たしかに、今日の経験は自信になりますね(笑)」
とぼけた会話である。でも、体感であり実感であった。
私はその日、大きな人に話を聞く喜びに首まで浸かってホッカホカになった。
だから「そういう発想」にたどり着いたのだ。
3日後。ウェブ企画を取り仕切った医学書院のHさんから、別件の相談と題したメール。「がん病理」の本をこれからつくるとしたら、どういうつくり方があり得るでしょうか、といった内容。それは必ずしも私への直接の執筆依頼ではなかったのかもしれないが、私は、そういった本を自分が書くとしたらと、当然のように考えた。
そして返事をした。……かなり長いが(すみませんでした)、引用する。
さて「がん病理の本」ですが、これについては常々考えておりまして、どのレベルの本がどれだけ世にあればいいのだろうと昔から悩んでおります。Robbins Pathologic Basis of diseaseを教科書にして、全国の病理学教室が医学生に「がんの講義」をしているのですが、それがきちんと診療現場のレベルでワークしているかというとなかなか微妙です。したがって、「現場でがんの知識が欲しい人」や、「医学部3年生ぐらいのときに聞いたっきり追加で勉強していない腫瘍学を、あらためて学びなおしたい人」は一定数いると思います。イメージとしては、感染症の本と同じくらいには需要はあると思います。が……作り方がすごく難しいですね。
現在、脳外科から産婦人科まで横断するがんの知識を持っているのは、腫瘍内科医と病理医くらいです。ほかは「自分の所属する科のがん」にだけ知識があるという状況です。さらに言えば、消化器内視鏡医だと、胃がんや大腸がんの診断をしているとしても、がん病理の知識なんてぜんぜんないです。診断のための知識はあっても、化学療法については「それをやりたい同僚におまかせ」だったりすることが多いです。
そういう、人によってがんとの距離がバラバラである状況で、「がん病理の教科書」があまりに総論的だと、逆に「だれのための本なんだ?」となります。「がんの病理」と聞いたら一度は読んで見たいと思うのが多くの(立場の違う)医師たちの本音ではあると思いますが、いざ開いてみて、各論が弱すぎるとウーンとなりますし、各論が強いとそれはそれで、お金払ったのに自分がぜんぜん関係ない脳腫瘍とか軟部腫瘍にめちゃくちゃページ割かれてるよ、みたいながっかり感が出たりもします。総論的なんだけど読んでいてワクワクしてなんか知識が増えるし、読み終わったらいろいろな臨床の感覚がふにおちる、みたいな本ってそれもう文学ですよね。
そもそも、それを書くのは果たして病理医であるべきなのでしょうか? 基礎研究をやっている大学の病理学者が書けば、分子生物学的な話に踏み込んで行くのはよいのですが現場のがん診療とは感覚がずれますし、診断をばりばりやっている病理医にしても今はサブスペに細分化されているために、詳しい臓器と詳しくない臓器の差が激しく、悪性リンパ腫の専門家だからもう20年くらい子宮癌を診断してない、みたいな人ばかりです。さらに、病理医だけが書くと、臨床画像との対応や再発の科学みたいなものも意外と書けません。弱点が多いんですよね。「病理学を全部書いたぞ!」と言われて読んでみて、たしかにそうなんだけど、標準治療の化学療法論とのかけあわせがぜんぜんされていないから、学問としてはいいとして実践であんまり使えないなあ、みたいな感想を持つ人は出てくると思います。いっそ腫瘍内科医が「がん病理」を書けばいいんじゃないかと思うこともありますが、がんの早期発見や予防といったよりプライマリに近い部分にかんする知識が少ないので、腫瘍発生やがんのバックグラウンドにあるリスクの話などが出てこないのです。
使い手も書き手もがんとの距離がバラバラ、な現状で、総合診療医や研修医などに、「がんを浅めに、しかし非医療者よりははるかに詳しく理解するための本」を用意するというのはもう激烈にむずかしいですね。著者選びには属人的なコネを超えた圧倒的な何かが必要だろうなと感じます。「がんとの距離感」が相異なる臨床医と研究者と病理医がみんなで作るということですよね。うまくいったら震えるほどいい本になりますけれど、へたすると「海外でめちゃくちゃ売れてる本の翻訳なのに国内では初版すらさばけないパターン」と一緒になるんじゃないかとも思います。
海外にそういう「がん病理」のバイブルとかがあるなら……と思ったのですが現時点で知りません。そういうのを知って、自分で翻訳したい、あるいは自分で書きたい、という人となると……仲野徹先生でしょうか? 一般書「こわいもの知らずの病理学講義」を医師向けにアレンジする、みたいな企画がじつは一番いいのかもなーとか思いました。すみません、思ったことをざっと書いただけですのでまとまりがないですが私の今の肌感は以上です。
がんをひとりで語ることは無謀だ。立場によってみな見え方が違う。
内科医ががんを語っても、外科医ががんを語っても、病理医ががんを語っても、それはがんの一部でしかない。それが悪いわけではない。専門家には役に立つ。局所では光り輝いている。
でも、「がんとは結局、なんなんだろう」を知りたい人たちへの手助け、第一歩にはなりづらいと思った。
そして、だから、つまり、「がんとの距離感がそれぞれ異なる人たち」とみんなで本を作れたらいいのに、と思った。
私の中に思い浮かんだのは、「インタビューと寄稿によって一冊の本をつくる」という体裁だ。まちがいなく、尾身先生との座談会から生まれた発想である。
ひとりで語れないならば、みんなにそれぞれ自分の強いポイントを存分に語ってもらえばいい。それを、横断的に各科とかかわる医師がまとめて一冊の本にする。
ただ、それは雑誌とどう違うのか、という懸念もあった。インタビューして寄稿を集めて作る、となれば、フォーマットが雑誌的になる。となると読者は「たった1号」では満足しないかもしれない。1巻で完結したアンソロ。2期の発表が来ないアニメ。
雑誌が悪いと言っているわけではない。そうではなくて、本を作った時の、ありようというか使命についてのスタンスのずれを気にした。
雑誌の重心とは、「繰り返し」と「更新」に対する責任に位置する。一方、単行本の重心は、「周りがいろいろと変わる中で、変わらないもの」を提示する姿勢に位置する。
私は、「がんの本」を作るならば、雑誌よりも単行本でありたいと思った。
「がんとはこういうものなのか」というのを知りたい、考えたい人たちが、いつまでも参考にしてくれるような、強い礎をつくりたかった。それは雑誌ではなかった。私が出すべきものは決定版であり、特選集のような単行本であった。
私がインタビューできるのは1か月に1人が限界だ。Zoomでのインタビューはなるべく避けたいので毎回出張になる。その手間という意味でも月に1名が限界。私の別件にあわせて出張の予定を組むことが多い。1冊の単行本を作るのに予算はそこまでかけられない。宿泊はできない。毎回強行軍だ。
だから体力的にいつもぎりぎりだ。そしてありがたいことに、インタビューはいつも、私のHPもMPも、ぜんぶ使い果たすくらいのものになる。
話をうかがった方々はみな、まるで違う視座から語る。
それはいつもの私からは見えないものばかりだ。
炸裂するような感覚があった。炸裂して、壁が破れて向こうが見える。私はその壁を、しかし、乗り越えることはできない。あくまで壁のこちら側にいる。しかし炸裂によって空いた穴から見えるものがおもしろくて、豊かで、美しくて、けっこう怖い。だから肉眼でも、双眼鏡でも、望遠鏡でもなんでも使って、そこをしみじみ眺める。壁の向こうに響く音に耳をすませて、聞き取って、書き取って、それをまとめていく。
ひたすら刺激的で、そしてものすごく体力を奪う作業だった。
その意味でも、1か月に1人が限界であった。
悩み、苦しみながら、インタビュー原稿を毎日いじった。
最初に企画のやりとりをしてから、じつに2年以上が経過していた。12人目が、設楽紘平先生であった。
インタビューが終わって、つくばエクスプレスに乗り、北千住でカメラマンのOさんと、秋葉原で編集者のHさんと別れる。そして山手線からモノレールに乗り換える。車内で私は、最近もうほとんど使っていないSNSに、感極まるように、このように書き込んだ。
設楽紘平先生とは何者かを知らなければググってみるといい。ああ、なるほど、すごい人だなと、みんなたぶん「すぐにわかる」。そして断言するが、しばらく後にできるはずのこの本の中で語る設楽紘平先生を読んでほしい。きっと、その「わかり」が吹き飛ばされる。楽しみにしておくといい。あんなものじゃない。