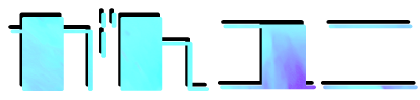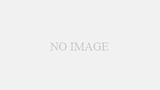0|0
15人までは決めていた。
「がん」をいろいろな角度から見ている人たち。
これまですでに、日米それぞれの基礎研究者、大学病院の病理医、腫瘍内科医、放射線科医、精神科医、緩和ケア医などからお話しをうかがうことができた。これらの人たちのみる「がん」というものはいずれも、びっくりするくらい違うもので、それが私にとってはとてもおもしろかった。
私ひとりが見ている「がん」とはこうも違うものなのか、と思ったし、逆に言えば、世の中の誰もがその人なりの「がん」を見ていて、それはきっと、少しずつ重なるけれど少しずつ違うのだろうな、ということをぼんやりと考え続けた。
ただ、そんなインタビューの日々に出会った、国立がん研究センター・がん情報サービスの若尾先生が言ったことがひっかかっていた。
「患者さんですよ。患者さんから話を聞いて私たちはいろいろなものを整えてきた。」
私はここまで医師にしか話を聞いていなかった。このあと、幾人かの「非・医師」にも話を聞く予定は組んでいる。
しかし、どうも、それでもなお偏っているのかもしれないな、ということが気にかかった。
若尾先生に、「だれかお話しをうかがったらいい人、思いつきませんか」と尋ねてみた。すると彼は言った。
先生の住んでいる北海道に、うってつけの人がいますよ。
北海道ですか? あっ、でも、お気遣いは無用です。私はこの企画ではとにかくどこにでも行くつもりなので。遠くてもかまいません。
いや、それはすばらしいことです。しかし、北海道の岩本さんは、それでも適任だと思う。
若尾先生は、なんだか、胸を張る感じで、そうおっしゃった。
60代前後と思われた。終始柔和なお顔をなされていて、そのたたずまい、ふんいきは、私がこれまで考えていた、「新聞記者」とは、けっこう違った。
お話しをうかがうのを食事の場にしたのは間違いだったな、と、今は思う。彼はとても誠実な方で、2時間近いインタビューの間、とうとう、ほとんどのものを口にすることなく、慎重に慎重に言葉を選びながら、「医療」を取材してきた彼自身の目線を私に共有してくださった。刺し身が乾くのに十分なだけの時間があっという間に過ぎ去っていった。
岩本さんが語ったことの中でわあっと思ったことは、彼が、「書くだけじゃだめなんですよ」と言ったことだ。新聞記者がそれを言うのか、と私は驚いた。しかし私は逆に、彼が、「書く以外のことはあくまでボランティアだ」と考えているのかもしれないと思った。そして彼はまさにその「書くこと」によって、実際に医療の現場を動かしてきていた。
私は25年ほど前に、彼の書いた記事を読んだことがあるようだった。新聞記者の署名を覚えていたわけではない。ただ、がん患者、家族、遺族たちが、20人以上グループになって、富士山を登山したという話を、私は確かに医学部生時代に読んだか聞いたかして、その光景を今も忘れずに覚えていたので、彼がたまたまその記事の話をしたときに、あまりに驚いて、思わず手元にあったビールを飲んでしまった。インタビュアーとしてかなり失礼だったなーと反省している。