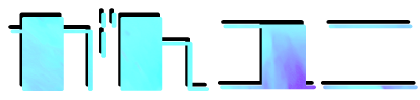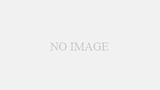0|0
しとしと雨の札幌に帰ってきて、いったん家に寄ってネクタイを付ける。インタビューも大詰めだ。あと2人。最後のピースのひとりに会いに行く。
本日、お話をうかがう場所はテレビ局である。最初、ここでやりましょうと言われたとき、ちょっと興奮してしまった。テレビに映るわけではないし取材を受けるわけでもない。なんなら今日は私が取材をするほうなのだ。でもなんだかうきうきしてしまう。天井高くに全国的知名度をほこるあのマスコットが鎮座する垢抜けたロビー。一時代を風靡したあのシリーズのDVDセットとグッズがところ狭しと並ぶ。視聴率競争の勝ち名乗りに忙しいノボリの文字に目を走らせていると、エレベーターホールから阿久津さんが降りてきた。
ようやく会えましたね。
ようやく会えました。
阿久津さんのことを最初に知ったのはいつだったかもう覚えていない。昔のツイッターアカウントで相互フォローだったきっかけも特にないと思う。かつての私はそれくらいたくさんフォローしていた。そんなフォロイーの中でも、阿久津さんのインパクトは頭一つ抜けていた。社交辞令とかではなしに。間違いなく今日まで、がっちり記憶に刻印され続けている本の作者。書名を、『おっぱい2つとってみた』という。
阿久津さんは北海道テレビ(HTB)のディレクターだ。入職のころから「がんのドキュメント」に並々ならぬ興味を抱き、20年ちかく乳がんの患者を取材し続けてきたら、なんと自分も乳がんになった。それも、両側。阿久津さんは主治医にがんを告知されるタイミングから自分で診察室にカメラを持ち込み、主治医に許可を取ってその風景を泣きながら撮影し、みずからの闘病をそのままドキュメントにした。類を見ない番組は世界的に有名となった。
私は、そのことを阿久津さん自身が書き取った本を読んで、ぶっとんでしまった。展開のすごさにではない。本の細やかさにだ。「がんになっても人生は続く」という強烈なメッセージは、しかし、観念やら情念やらで語られるわけではなく、「ここに頼ればいい!」「ここと相談できればいい!」という極めて豊富で緻密な「具体」によってしっかりとサポートされていた。
「がん患者の気持ちはがん患者にしかわからない」という言葉に、私はかねてより懐疑的であった。がんといっても、ひとりひとりまるで違う。Aさんのがんの体験がBさんにうまくはまるわけではない。幡野さんもかつて言っていたが、がん患者が「患者ブログ」を当てにすることには大きなリスクが伴う。しかし、阿久津さんに会うと私の意見は少し変わった。「がん患者にしか生じない気持ちを、『伝えるプロ』がしっかりアレンジしてがん患者にシェアすることは、とても有用なのではないか」。阿久津さんはがん患者であり、がん患者の家族でもあり、がんのドキュメントを撮り続けたプロでもある。そのことがどれだけ多くの人の支えになっているかということを、私は阿久津さんの番組や本を通じてこれでもかこれでもかと思い知らされた。「がん患者の悩みごと、迷い、願いをシェアすること」に、私はもう一度、きちんと向き合おうと思った。これをきっかけに私は、中島ナオさんや井出智さんなどの「声をシェアしようとがんばるがん患者たち」の声に、それまで以上に興味を惹かれることになる。
2時間をオーバーするインタビューの末、へとへとになりつつも、私は編集者とうなずきあった。「これはいい本にしないとだめですね」「いい本にしましょう」。がんのことをさまざまな角度から語ってもらうという本書『がんユニバーシティ(仮)」に、医者や看護師だけでなく、「患者」をお招きできて本当によかった。それも、「自分の体験を語る患者」というわけではなく、「患者の身になって必要な話を追い求め続ける取材者」の話を聞けたことは、この本にきっと大きな福音をもたらすだろう。
帰宅、翌朝、一通のメールが届いた。来年のとある学会の大会長からの、依頼のメールであった。そこにはとても丁寧な筆致で、「今度の学会で、◯◯がんについて講演してほしい」という依頼が書かれていた。もちろん二つ返事で引き受けよう、そう思ってメールソフトに向き合って、しばらく、私はうまく文章が書けなかった。「がんについて語る」というとても大きな仕事に対するふるえのようなものが、足元から込み上げてきて、両手の薬指や小指がかたかた震えてキーボードがカチカチ鳴るのがわかった。なるほど、これはこういう仕事なんだよな、と、これまでたくさんの人に話を聞いてきた私は、今更ながらに、思い知った。