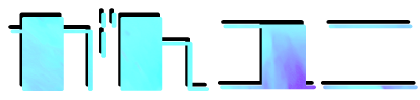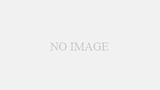0|0
羽田からリムジンバスで豊洲に直行。豊洲駅のまわりでなにか食べようかと思ったが街は猛烈に熱せられたジュラルミンのようであった。とりあえず昼飯は後回しにしてゆりかもめに歩く。目的地は「市場前」。
市場前の二階改札を出て、そのまま直進しても左折しても観光客ルートだ。しかし私は右折して待ち合わせの場所に向かう。ラビスタの手前にあるオフィスビルに、広い待合スペースがあると聞いていたのだが、そこの利用可能日はどうやら平日だけのようで、大型のガラスの向こうはしずかに暗くなっており人影がない。集合時間は12時半。日陰でもじわりと暑い。見回すとサンドラッグと遠くにセブンイレブンがある。どちらかで昼飯を買えるだろうが、まだ30分あるのでやはりどこかの店に入ろう。しかし市場駅の人の多いほうに行くとおそらく観光客価格の海鮮丼とかを食べることになる、気後れしていると、ラビスタの眼前に、おそらく宿泊客に朝飯を食わせたり、オフィスビルの社員たちにランチを食わせたりしていそうな和系の飲食店がある。ふらふらと近寄っていく。自動ドアを一歩入ると雰囲気はおもいきり最近の居酒屋風味、店員がいちいち若くかわいらしくすごくラフな話し方をする点もなんだか完全にチェーンの居酒屋であった。客はかなり少ない。通された席はカウンター。大将感のあるベテラン男性がひまそうにまな板などを磨いている。まったく味に期待せずにメニューを開くと日替わりのランチがまさかの1200円、おっ、東京価格とは思えない、えっ、これ何が出てくるんだろうと思いつつも注文してちょっと待つ。眼前の大将が料理するのかと思うと、しない、なるほど、奥から運ばれてくる。しかもわりと早い。出てきた料理は小鉢も含めてわりとしっかりいい見た目で、箸をつけるとぶり大根のしっかりうまいことに度肝を抜かれる。味噌汁の具も多い。ねぎとろなんかも細かくうまい。帰り際、思わず大将風の男性に「これおいしかったですね……」と、感想というか吐息のようなものを伝えると、ものすごく接客慣れしている朴訥キャラ、といった風情で返事をくれた、そういったところすべて含めて存外に好感度が高かった。
「季(とき)の庭」という店。まったく期待していなかったのにそうとう満足をした。やはり出張のときの昼飯は「チェーン居酒屋の昼営業」に限る。
12時半、いつもの編集者Hさんと落ち合う。そこにはもうひとり、本日おたずねする秋山正子さんと長年懇意にされてきた編集者のAさんがいらっしゃっていた。人懐っこい方で、かつ、なかなかの量の汗をかいている。これは北海道に住んでいる人間だとあるいは共感してくれるかもしれないが、私は東京や大阪に来て夏の暑さにどっぷり浸かることをかなり恐れており、しかもそこで、「慣れていない暑さの中でひとりだけ大汗をかく」ことにけっこうな羞恥心を覚える。そんなとき、現地で暮らしている方々が普通に汗をかいているのを見ると、「なんだ、内地の人にとっても今日は暑いんだ」と思ってひどく安心をする。許された感覚になる。この日の私は、昼飯にしても、初対面の相手の印象にしても、順調に安心を積み重ねていて、「おそらく運が向いている日なのだ」と思った。いつものカメラマンのOさんとも合流。ラビスタのロビーで少し涼んで、歩いて5分もかからないという目的地に向けて、ものすごい日差しの中を歩く。
マギーズ東京。
ついに訪れた。
西智弘が書籍に書いていた。
鈴木美穂さんがよく語っていた。
雑誌「Cancer board square」で読んだ。
テレビで見た。ネットで見た。たくさんの人の口から耳にした。あのマギーズ東京だ。いつか来たいと思っていた。
場外市場からも、がん研有明病院からも、国立がん研究センターからも、2.5次元シアターの聖地からも近い、クラフトビールを売るキッチンカー、水面で爆発する太陽光、ベビーカーと木陰で休ませる人、汽笛、ありとあらゆる人工物と自然物から近い場所にそれは建っていた。銀色の街の中に突如としてあらわれたそれは確かに庭であった。周りの風景がぐっとぼやけてそのちっぽけなおうちは柔らかくオレンジ色に輝いた。かつて、父母が仲良くテレビで見ていたハーバリスト、ベニシア・スタンリー・スミスさんの家のことを思い出した。
秋山さんにうかがったお話しは本とウェブで世に出す。それぞれにどのような按分で公開するかは今後熟慮するけれども、おそらく、どこもカットせずにすべてを出すことになる。あの貴重な時間のすべてを多くの人に見てもらいたいと私は思った。秋山さんは小柄な方で声も小さかったがとても聞きやすく、そして、それは確実にある種のカリスマ性の種となるものではあったがしかし秋山さんの本質はそこにはないのだろうと私は思った。秋山さんは、相手の期待しているものも、相手の失望しているものも見逃さない眼力と、情報の流れが一方的にならないような気配りがあり、それはおそらく秋山さん固有のもの、すなわち素養というか資質というか才能に属するもののはずなのだけれど、なぜか、不思議なことに、「自分もこうありたい」と私をはじめ多くの人間が意を決する、秋山さんのようになって多くの人とコミュニケーションを取り続けたいと思わせるようなとても不思議な魔力で、つまりは「こうなりたい、とはとてもおこがましくて言えたものではないが、こちらの方向に歩きたい、と思うことを全力で応援してくれる人」なのであった。
Aさんがつぶやいた、「ここができて10年くらい建っているのにまだ木の匂いがする」という話を、秋山さんにそのまま伝えたら、「この木はいいですよ。ほんとうは捨てられるはずだった、モデルハウス的なを再利用したものなんですけれどね。ぜんぶ国産の木でね」と、うれしそうに言った。梨を出してくださった。食べた。カメラマンのOさんが、「今年はじめて梨を食べましたよ」と、これまたひどくうれしそうに笑った。