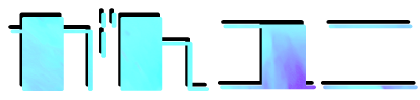6|15
生まれたばかりの赤ちゃんの、消化管の顕微鏡像がどんなかんじなのか。教科書をひもといて調べている。べつに趣味でやっているわけではない。仕事の一貫だ。
病理診断をやるうえで、正常と異常とを見分けるのは大事なことである。正常といってもいろいろだ。バリエーションがある。正常という座標があるわけではない。正常とは範囲で示される。
さらに、「生まれてこのかた変わらないもの」と、「生まれてから徐々に変わっていくもの」とがある。子どもが大人になっていく過程で、肝臓や腎臓はどんどん大きくなるし、胸腺は逆に小さくなる。虫垂はいったん大きくなってから途中で少しずつちぢんでいく。この変化も含めて正常。これらはぜんぶ、そのときどきの正常なのだ。
勘違いされがちなのだけれど、正常を勉強するということは、異常を勉強するのと同じくらい、手間がかかる。正常はひとつで、病気はたくさん種類があると思っている人もいるかもしれないが、そんなことはない。
今、私は、「消化管の中で、赤ちゃんのころから変わらず存在する細胞」を調べるため、新生児や胎児の臓器の顕微鏡写真が掲載された英語の本をゆっくり読んでいる。主細胞って生まれた直後は思ったより少ないんだな、とか言いながら。
写真のキャプションに、◯週、◯日、という短い解説がついている。
妊娠◯週で生まれ、お腹の外で◯日だけ生きた、という意味だ。
なんらかの理由で亡くなってしまった赤ちゃんの臓器を顕微鏡でみて記録したもの。それを読むことで、私たちは、人間が胎児から大人になるまでどうやって変化していったのかを知ることができる。
考えてみればあたりまえのことだ。
しかし、読んでいると、やりきれない気持ちになる。
この教科書の著者たちは、◯週、◯日ということばを、ぼかしたりはぶいたりして、およその時期と写真だけで説明することもできたはずだ。でも、そうしなかった。いくつか理由があるだろう。学術的な理由もあるとは思う。でもそれだけだろうか。
思うところがあったのではないか。先輩たちもきっと。