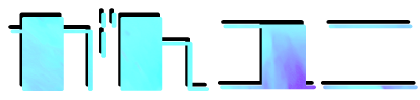22|22
13,4年くらい前のこと。私はまだ30代前半であった。大学院を出てから数年、病理医としてはまだまだ若輩、しかし、専門医も取得し、自分の裁量である程度仕事ができるようになって、少しずつ自信もついてきたころだ。
縁あって、診療放射線技師の会に呼ばれる機会が増えていた。胃のバリウム検査に従事する技師たちは、技術を磨き精度を高めるために頻繁に研究会を開催している。そこに私は呼ばれて病理の講演をした。
ベテランの技師たちから問われたことを必死に勉強して自分なりにプレゼンテーションにまとめる。胃癌とは病理医からみるとどのような形態なのか。分化型、未分化型。消化性潰瘍。癌の深達度によって癌の見た目がどのように変わるか。「お題」はいくらでもあった。
それは研ぎ澄まされた学術講演とは程遠い、粗く偏った自説の展開であったが、彼らはいつも喜んで受け止めてくれ、そればかりか、「忙しすぎて話しかけるのもはばかられるようなエライ大学教授に高い講師料を払ってしゃべってもらうよりもよっぽどおもしろいよ!」と、私を全肯定してくれた。
私はちやほやとされ、半年後に1時間半しゃべってくれ、1年後には1時間しゃべってくれ、次は横浜だ、次は大阪だと、引っ張りだこになりつつあった。
通算5回目くらいの講演を終えた日だった。私は「懇親会」で酒を飲んでいた。1次会には30人くらいの放射線技師が集まって、私はたくさんの人と乾杯をしたり研究会の症例の話をしたりして盛り上がった。2次会はすすきのの少し南の方にある、古い雑居ビルの中のとりわけさびれた味のあるスナックであった。
スナックと書いたがかなり店は広いのだ。軽く20人以上がゆったりと座れ、部屋の真ん中にコの字のかたちにカウンターが置かれていて、ウイスキーに水を入れるためのプッシュ式のポンプみたいなのがあった。私は隣に座っていた技師さんたちの前を手刀ですみませんすみませんと避けて通り、カウンターに向かってグラスに水を足そうとした。
するとそこに先にいた、背の高い、おそらく40代くらいの技師がこちらをくるりと振り返って言ったのだ。
「あんたさあ、あんまり調子に乗ってんじゃねぇぞ」
私は全身が一気に動かなくなってのどが詰まったまま立ちすくんだ。その人は、一言だけを私に投げつけると、部屋の反対側に向かってスタスタ歩いていき、何事もなかったように他のスタッフといっしょに談笑し始めた。
あれはなんだったのだろうと今も思い出す。というか、忘れたことがない。
心当たりがなかった。そもそも初対面だった。個人的なやりとりによって相手を怒らせたのではなかったはずであった。
何日か経ったある日、そうか、私はもしかしたら、講演で彼の言うとおり、そのままの意味で、「調子に乗っていた」のかもしれない、と思った。
この話には答えがない。その方とはその後お目にかかっていない。次の学会でも、その次の研究会でも、私は会場でその方の姿を探したが、二度と私の目に彼の姿が映ることはなかった。おそらく彼は本当に怒っていたし、その後、私が出る会となれば、あるいは避けていらっしゃったのではないかとも思う。
飲み会の1次会や2次会の、なにかの会話で私が失礼なことで盛り上がっていたとか、そういう、ピンポイントのやらかしがあったのかもしれない。そのような可能性については何度も考えた。でも、いつも最後には、おそらく、私は、いくつかの具体的にエピソードで彼を怒らせたのではなくて、「診療放射線技師に対する態度や雰囲気のすべて」で彼を怒らせたのだろうなと、ぼんやりと胸の奥が痛くなる最悪の推測が正解なのだろうなという気持ちになっていった。
謙虚さは足りなかった。視野は狭かった。しゃべりくちが傲慢だった。ベテランの技師たちが気を遣って立ててくれていたことに感謝もせず配慮もしなかった。自分の倍くらい生きている技師たちに向かって上から目線で何かを教えてやるという気持ちで過ごしていた。それを技師たちはがまんしながら、私の口からなにかひとつでも病理の役に立つ話が出てくるのではないかと、さほど精度の高くない私の話をしんぼうづよく聞いてくださっていた。
すべては推測だ。しかし、当たらずとも遠からず、だったのではないかと思う。
少なくともあの日、スナックで棒立ちとなるまでの私は、私に機会を用意してくれ、私の話を聞いてくれた人々が、私をどう見ているかということを、それほど真剣におもんぱかっていなかった。
いつも、自分、自分、言われたことをどこまで越えていけるかという、自分のことで頭がいっぱいだった。
このことをきっかけに、私の行動がガラッと変わった……と書けば、それはいかにも青春小説のようなわかりやすい展開だが、残念ながら、そうではなかった。
私は突然の「怒られ」のあと、もしかしたらあの人は酔うと怒るタイプの困った人なのかもしれないな、とか、ほかのスタッフたちは相変わらずほめてくれるからやっぱり私は別に間違ってないんだろうな、といった、「ポジティブな結論に持っていけそうな証拠」を無意識に探し回った。言葉で殴られたがじつは殴り返してもよかったのではないか、あのときああ言い返していればどうなったろうか、といった妄想にもふけった。講演の依頼はあいかわらず止まらなかった。もし仮に彼が言ったように、私が多少なりとも調子に乗っているとしても、これは、実際に調子に乗っていいのではないか、それくらいのことを私は今やっているんじゃないのかと、折れた鼻をもう一度伸ばすくらいの気持ちでいた日もあった。
ただ、彼のあの、私より高い位置から三白眼で私をにらみつけたときのあの顔は、ふとした瞬間に思い出された。
図に乗って走り出しそうな気持ちにかかるエンジンブレーキであった。
ちかごろの私は毎回、講演のたびに、直前に、本当に毎回、あのときの彼の顔を思い出す。まるで三文小説のような書き方になっているけれど残念ながら誇張ではなく完全にそのままの意味なのでこれ以上に書きようがない。
私は今回の講演をだいぶ調子に乗って作ったのではないか。私は今日これから話をする学会の聴講者たちをどこか上から見ようとしているのではないか。私は今日、だれかに、調子に乗ってんじゃねぇぞと、学会会場の出口で、電車のホームで、空港で、SNSで、ぼそっと、しかし敢然と、怒られるのではないか。
そのようなおそれの気持ちは日に日に強くなっていく。
先日、ある学会の懇親会でお目にかかった方が、ワインなどを飲みながらこう言った。「先生はずいぶんとまあうまくしゃべるけどそれって練習してるの? しゃべる練習。すごいよねえ」。私は答える。練習してます。これまでもずっとですしこれからもたぶんめちゃくちゃします。練習しても、いくら練習しても、だめなんですよね、しゃべりのうまさだけ届いて内容が届かなかったりする。私のキャラクタだけ届いて学問のことが出てこなかったりするんですよ。本当に私はもう、まだまだ、ぜんぜんだめで……だめで……。一斉にまわりがつっこんでくる。またまたァ! またまたァ! いえほんとうに。いえほんとうに。
いえ、ほんとうに。これはもう、誇張でもなんでもなく、ほんとうに。