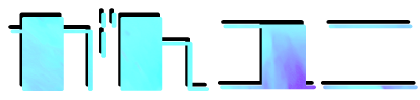19|7
「さじ加減」という言葉がある。もとは江戸時代あたりだろうか、医者が薬を煎じるにあたって、生薬的なものをごりごりとすりつぶして混ぜるわけだ。その分量・組成のレシピはあらかじめそこそこ決まっているのだけれど、実際の運用にあたっては、患者のようすを見ながら、こっちの黄色い粉末をちょっと足したりこっちの汁気の出るやつは少し減らしたりといった感じで、おおさじ・こさじの具合を調整していく。その姿を「さじ加減」と呼んだのだろう。
ほんとかな? いちおう語源調べとくか。あってるっぽいな。あってます。
で、こういう、足したり引いたりできる治療というのはかゆいところに手が届きそうな一方で、「それって結局医者の主観じゃん」みたいな話もある。現代の医療だとさじ加減なんてものは許されない、エビデンスだ、特茶研究所だとかまびすしい(私は特茶研究所のことはまだ許していない)。
ただ実際に友人たちの話を聞いていると、現代の医療もまたさじ加減は必要なのだ。というか、医者の仕事の多くはさじ加減なのかなとも思う。
科学の粋を集めて作った抗がん剤にしても、患者の体重であるとか、代謝のぐあいであるとか、あるいは最終的におしっこにして流していくための腎臓の機能であるとかをきちんと考えて、量を細かく設定しなければいけない。
点滴だってそうだ。中には「よっぱらったときに点滴入れてもらったら具合がよくなった」みたいな謎のシチュエーションしか思い浮かべない人もいると思うけれど、そもそも人間の体というのは、水分のイン・アウトをめちゃくちゃ細かくコントロールしているので、人の手でそこに水分を足したり引いたりするというのは細心の注意をもって行わないといけない。なんでもかんでも点滴入れておくと患者の体内に水分が多くなり、ひどくすると肺の血管がふくらんだり水がもれたりして「おぼれて」しまうことにもなる。
こういったファクターを、コンピュータでもAIでもなんでもいいから、とにかく客観的に評価して、科学とエビデンスと特茶研究所で(※まだ許していない)理論的にやっていきたいと思うのはやまやまだが、はっきりいって、「経験を積んだプロが患者の全体的な雰囲気を一瞬で悟って把握して、それを治療に反映させるときのさじ加減」のほうが圧倒的に小回りがきくし切れ味も鋭かったりする。
ところで病理医は薬を処方しないし、処置も手技もほとんどないので、さじ加減的なものを発揮するシーンがほとんどない。……と、私自身もわりと長く考えていた。
でも最近、あるな、と気付いたことがある。さじ加減が。
それは臓器を切り出すときのナイフの角度であったり、遺伝子検査を提出するときの項目の選定方法であったり、あるいは報告書を書くときの文面の「迫力の部分」であったりして、どうにも、言語化して説明することが難しいものばかりなのだけれど、どうも私もまた、エビデンスを逸脱しすぎない程度に自分の診断を微調整する行為を日々やっているようなのである。こないだ特茶飲んだけどおいしかったよ。けど特茶研究所は許さないよ。