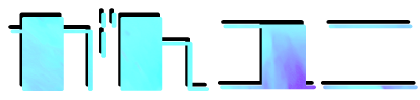14|12
がんとは特殊な病気だろうか?
少なくとも私は、小さいころから、わりとそう思っていた。
今でも、がんという言葉にはかなり強い圧があると感じる。ほかの病気とは違う、絶対的な圧が。
最初にがんの圧を浴びたのは小学校のころだ。
私は札幌市の中心を走るバスに乗って、駅前に向かっていた。窓の外を見ていると、「北海道がんセンター」という文字が目に入った。「がん」というひらがなが、突然脳の中をかきみだした。となりにいた母に、私はたずねた。
「がんセンターって、がんの人が集まってくるの?」
区民センターには区の人が集まってくる。しかし、それと同じように考えてよいのだろうか。「がんセンター」とはなんとひどい名前なのだろう、と私は思った。
「がんになって、がんセンターに通うなんて、いったいどんな気持ちだろう。自分だったら耐えきれない」
何を読み何を聞いたのかはわからないが、当時、私はがんイコール死ぬ病気と考えていた。治ることもある。しかし治らないことが多い。ただ、ただ、かわいそうで、気軽に触れてはいけないもの。がん患者は、ベッドに横たわってほとんど何もできなくなる。衰弱して死んでいく。それをまわりが悲しみながら見届けていく。そういう病気だと考えていた。
だから私にとって、まちなかに堂々と、「がんセンター」という看板が掲げられていて、玄関から普通に「がん患者」が出入りしている状況にとても驚いた。
しかも驚いただけではなかった。
がんセンター、なんて命名、ひどい。
ここにかわいそうながん患者がいると、見せびらかすなんてひどい。
おそらく私は怒っていた。
そのうち私は、「がん」を仕事にしている人間のことにも思い至った。当時、NHK教育テレビでは、「はたらくひとたち」というタイトルの番組をやっていて、私はたくさんの職業人のことをなんとなく知り始めていた。中には医者という仕事も含まれていた。しかし、私は、「がんセンターではたらくひと」のことを、これまで見知ってきた職業とはまるで別様に感じた。
なんと怖く、得体がしれない仕事なのだ。「死が見え始めた人」の前で働く仕事なんてまっぴらだ。
中学、高校、大学と進学していくうちに、私はいつしか、「がん」という言葉の圧を最初に受けたときの嫌悪感をわすれた。しかし、「がんは特殊な病気だ」という最初の印象だけは消えずに残った。
これが、誰にとっても共通の感情「ではない」ということを知ったのは、つい最近のことだ。
がんとは、もはや、特殊な病気ではないと言う。一人や二人がそう言ったという話ではない。わりとたくさんの人たちが、「数ある病気のひとつでしかない」と言う。
私はそのことにとても驚いた。まだ驚いている。驚きながらこのブログを書き続けているし、インタビューを続けている。