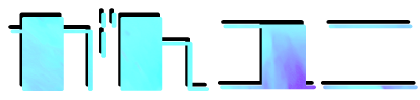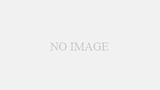22|24
若い人と一緒に顕微鏡を見る。そういう専用の顕微鏡がある。鏡筒の部分が分岐していて、視野をシェアできる。最近は、デジタルパソロジーと言って、プレパラートをデジタル化してオンラインでみんなで見る形式もあり、それだと画面上で文字とかも書けるから便利じゃん! みたいなことも一時期は思った。でも、アナログな顕微鏡のほうが動作が0.2秒くらいずつ速い。やっぱ最後は速さが正義だよなという気持ちがある。いや、今日は、そういうデバイスの話をしたいわけではなかった。
若い人と一緒に顕微鏡を見る。若い人が診断文を書いたものを、電子カルテに送信する前にチェックするという仕事だ。「この病変、良性でいいですよね?」「いいですよ」「良性の、◯◯症でいいですか?」「うーん、というよりは、良性の◯◯腫のほうがいいんじゃないですかね」。
線を引く。
病気という概念の中に線を引く。
おおざっぱに二つに分ける。
良性の島 / 悪性の島
ゴリゴリぶっとい線で明確にわかれるかというと、じつは、中間的な部分もあるので、必ずしもそこを分けるのも簡単ではないのだが、中間的な部分もあるよねと、みんなと納得していれば、運用上はなんとかなる。
おおざっぱに二つに分けた、良性、悪性、それぞれの中に、さらに線を引いていく。良性の中でも◯◯症という島がある。それとは別に、◯◯腫という島がある。若い人はひとまず、今回見ている病気を、「◯◯症」の島のなかにくくろうとした。しかし私は顕微鏡を見て、今回の病気は、その島から2歩ほど外にはみ出しているのではないかと考えた。
分類というのは、「はみでること」を前提として行う。クリアカットに分かれるなんて最初から思わない。今見ているものが、ここかな? ここに入るかな? この島に入れていいかな? この箱に入れていいかな? でも、「はみでる」なあ……というのを繰り返す。情報を更新していく。その作業の積み重ねを分類と呼び、診断と呼ぶ。
「この病変、◯◯症としても悪くはないんですけれどね。◯◯症だとすると、この性質が、はみでますよね」
「なるほど、はみでますね」
「だったらこっちの◯◯腫の島に入れたほうがいいんじゃないですかね」
「なるほど」