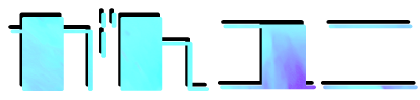27|2
今日はがんばかりであった。浸潤範囲が予想よりやや広いもの、組織型が典型例より悪いもの、リンパ管侵襲が多いもの、やけにそういう症例ばかりが目につく日だった。
何年も前のこと。生検のチェックをボスにしてもらったあと、「目合わせ」をするために一緒に多筒顕微鏡を見ていたら、30代の胃癌患者の生検を見たボスがひとこと、「かわいそうになあ」と言った。私は、瞬間的に撃ち抜かれた気になった。
私たち病理医は1日に何十人も患者をみる。一般的な臨床医が一日の外来で出会うよりも多くのがん患者を見ることもしばしばだ。その代わり、私たちは、一人ひとりの患者の顔も見ないし声も聞かない、ただ、細胞を見て診断を確定するだけである。だからこそ、だからこそ、病理医はその重い責任に耐えられるのだろうと若い私は考えていた。ボスから出てきた「かわいそうになあ」は、熟練の病理医が細胞の向こうにいる患者にいちいち思いを馳せているということを意味していた。私はそのことに慄いた。何十年もはたらいて、「悪性」と判断することがいいかげん作業になっていてもおかしくないはずのボスの口から出た「かわいそうになあ」は、私の心のよこっつらをひっぱたいた。
そうか。病理医も患者を思っていいのか。
私はこんな当たり前のことに気づくのに何年もかけていた。
今日はがんばかりであった。仕事を終えて帰路、座席の上で私は大きく放屁した。いつものことだ。日中、診断している間、私の腸は動かなくなる。帰る途中に思い出したように動き出して空気のような屁が出る。今日はがんばかりであった。