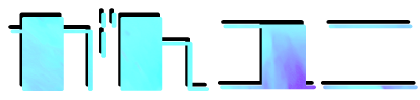※毎週火曜日、書籍『がんユニバーシティ』で行ったインタビューの、「編集中の原稿」を全文公開します。書籍版ではここから大幅に編集をし、各先生方からの寄稿をはじめとするたくさんの文章をコラム的に散りばめて、一冊の本にまとめます。このブログでは、インタビュアー(市原)が興奮し続けた「生の雰囲気」、編集前の原稿だけが持つ猛烈な(ちょっと読みづらい?笑)エネルギーを味わっていただきたいと思います。
科目名: 腫瘍内科
講師: 設楽 紘平 先生(国立がん研究センター東病院消化器内科)
テーマ: がんを薬で治すということ
学期: 2年前期
Q & A
Q1. 設楽先生のご専門と,お仕事の内訳をお教えください.
A1. がんを内科で治療する医師です.
立場は,消化器内科の科長です.併任として新薬開発部門に関わったり,先端医療科といって第I相試験をやっているような部門にも関わっていますが,メインは消化器内科です.日常の業務の主な部分は外来ですね.
当科には若いレジデントも入れると20人くらいドクターがいますが,なかには研究を中心にやっているメンバーも,臨床をメインでやっているメンバーもいます.僕は,臨床のウェイトが多く,月水木金,週4日,ひたすら外来に出ています.一日40人くらいはだいたい診ています.
外来の中から入院する患者さんも多くいます.消化器内科全体で,今は平均して70~80人が入院しています.抗がん剤のために入院する方もいらっしゃいますが,最近の抗がん剤は外来でもできますので,新しい薬の治験のためとか,症状緩和とか,幅広い目的で入院されています.
入院された患者さんは,基本的に比較的若い先生,レジデントの先生に診ていただくんですけれど,一緒に相談する必要もあるので,朝の回診はみんなでやります.回診して,外来があって,あとは,それぞれのカンファレンスですね.胃がんのカンファとか,大腸がんのカンファとか.
研究はどうかというと,コラボレーションが多いですね.臨床をやりながら,病理の先生とか,免疫の部門とか,ゲノムの部門とか,ときどきカンファレンスをしながらみんなでやっています.
あとは,製薬企業とか体外的なコラボレーターも多いので,そういう人たちとの面談もあります.今はテレカンファレンスが多いですけれど,日本の方とは日中,外来終わってからの午後4時くらいが多いです.海外とは朝と晩ですね.
Q2. 設楽先生にとって,がんに携わるとはどういうイメージでしょうか.
A2. 患者さんを良くする.
患者さんを良くする.患者さんをハッピーにできる.それが臨床医としての醍醐味ですよね.とにかく良くする.それが大事な仕事かなと思います.
細かいことを言えば,がんを持っていても普通の生活ができる方も多くなっています.でも,それもまとめて,とにかく良くする,ということです.
「がんを薬で治す」って,もちろん,それは常に目指したいし,ちょっとずつ治るケースが増えていますし,夢でもあるんですけれど,現実的なところとしては,治すにしても,治すまでいかないにしても,とにかく良くしたいですね.
Q3. がん医療やがん研究に従事するにあたって求められる,専門性や職能(スキル)は何でしょうか?
A3. コミュニケーションのスキルかもしれませんね.
難しいですね.でも,患者さんとやりとりをするっていうことと,やりがいを持つっていうことが大事なのかなと思います.
コミュニケーションができないと,臨床にしても研究にしてもつながらない.臨床メインであれば何よりも一番大事なのは,患者さんとの話とか,いかに一緒に治療していくかっていうことだと思います.「はじめまして」でスタートして,こういう病気で,手術が難しくてここに来て,薬がおすすめだけど,なかなか治るのは難しいよというのを,短時間で話をして,やる気になって帰ってもらうってすごく難しい.
そこを何とか前向きになってもらってっていうのは,スキルなのかもしれませんね.たとえば,話をするとき,病院だから当然マスクはしなきゃいけないんですけれど,ずっとマスクをしているとどういう顔かもわかりませんから,ときどき顔を見せてにっこり笑えるかという.
暗い話をどんよりしたまましてしまう若い医者もいます.「それだと患者さんも元気にならないから,ときにはもっと明るいオーラを出してみたら」と言ったりもしますね.
Q4. 医療従事者や研究者が修める,「がんの学問」(がん学)を想定します.それはどのような学問体系でしょうか.
A4. がん患者学,も含まれると思うんですよね.
生物学とか,がん自体の病理とか,その発生とか,いろいろ大事なんですけれど.
がんを持っているのは患者さんなので,がんを持った患者さんの経過とか,そうですね,あえてがん学というのがあるとしたら,「がん患者学」みたいな,そういうところは大事かなと思いますね.実際に治療している方がどうか,とか.
医学生がそこに親近感を持ってもらうということを考えるならば,やはり各病棟の見学に行けばそういうのに触れることもあるでしょう.患者さんから経験談を聞くってこともあるかもしれないですし,ブログとかSNSで見ることもあるでしょうし,ドラマを見ることもあるでしょう.そういうのも大事だと思います.
学問としてのがんだけじゃなくて,がんを持った患者さんの経験っていうのは,学問と言えるかどうかはわからないですけれど,そこをどうにかするということが結局,がんを学ぶ理由にもなります.
Q5. 「がん学」を修める学生たちが,心に留めておくべき「勘所」はありますでしょうか.
A5. 研究と患者さんとの距離は,遠くなりすぎないように.
当科には,臨床も勉強したいし研究もやりたいという若い方が来るんですけれど,「最初はちょっと違う」と言いますか…….若い先生は,研究と患者さんとの距離が遠いんですよね.
若い方々は,外来で目の前の患者さんと話していると,それはもう診療であって研究じゃない,というイメージなんです.机に戻って,じゃあ研究は何しようってなったりする.
カンファで患者さんの話をしているときも治療のことがメインになってしまって,研究だったらという視点がないですね.
たとえば外来で40人を診ながら,この人の経過がこうなのに,こっちの人はなんでこうなんだろう,じゃあこういう研究はどうかな,とか,この治療はみんなに効いたのに,この人にはなぜ効かないんだろう,じゃあこのがん細胞の検体を取って解析に回そうとか,そういうことの繰り返しだと思います.
いつもと違う患者さんを診たら,同じような患者さんがいないかなというのをPubMed等で検索する.目の前の患者さんと研究や文献をつなげるというのを,自然にずっとやる.
一般的な,教科書的なことが頭に入っているとして,それから逸脱したことが起きたら,何か調べるとか症例報告にしようとか,そういう頭で働くといいですよね.
愛知県がんセンターの疫学予防部の松尾恵太郎先生という方と一緒にいろいろやっていたときに,「とにかく臨床の現場っていうのは,みんな見過ごしてるんだけど,石だと思っていたものがダイヤモンドの原石だってことはよくあるんだよ」と言われました.それは本当にそのとおりだなと思います.
Dialogue
<患者さんが元気になるタイプの医者>
―――設楽先生のご来歴をおうかがいしてもよろしいでしょうか.
医学部に入る前,親が医者だったので,医者というのは比較的身近な職業でした.かつ,医学部は他の学部よりも,入った後の勉強がすぐ仕事につながっていくという印象がありました.受験勉強なんて,そんなに長くはしたくなかったので,入れる大学に入って,医学の勉強をさっさとはじめて仕事につなげたい,というイメージでした.
がんになる方,がんで亡くなる方は,私が医学部に入学した当時から多かったですし,テレビに出ている芸能人ががんになったとか,身近にがんにかかった祖父がいたこともあって,大学の早いうちから,がんに携わるべきかな,というふうに思っていました.ただ,手術は手先が器用な人がやるイメージで,それはもう自分に向かないかなと,早い段階から見切りをつけていました.なので,大学の3年目くらいには,内科でがんを治療するほうに関わっていこうと決めていたと思います.
―――親御さんが医者であった,というのも,「医者のイメージ」としてあらかじめ大きかったのかもしれませんね.親御さんはがんに携わられていたのでしょうか.
親は医者ではありましたが,医学の話がすごく身近だったわけではなかったです.うちの親は……怒られるかもしれませんが,一生懸命とか真面目にやっていたタイプではなくてですね(笑).勤務医だったんですが,子ども4人を養うために,私立の比較的大きい病院でずっと働いていました.一時期,研究をしていたときもあったみたいで,ちょっとがんのマーカー等の研究に関わっていたようです.でも,あとは一般内科をずっとやっていました.家で医学書を読んでいたとか,医学関連の仕事をしているところだとかは,全く見たことがなかったです.趣味があって,昔の切手を集めるのがすごく好きで,いわゆる「竜切手」とか「小判切手」みたいな,そういうのを集めていました.
家ではずっとそういうことをやっていたので,たぶん,僕の一番下の弟なんてのは,父親は切手屋だと思っていたんじゃないですかね(笑).切手の本とか写真集も出していましたから.
ただ,学生時代に1回だけ,親が勤務している病院を見に行ったことがありました.1回だけですがよく覚えています.回診や外来をしているところをちょっと覗いたんですね.そのとき,うちの親は明るく高齢者に接していて,みんな元気ににこにこ帰っていく感じだったんです.他の外来では,病気が違ったからかもしれませんが,医者はシリアスに,厳しく患者さんに接していたりして,けっこう違うもんだな,と思いました.父親のような,患者さんが元気になるタイプの医者はいいなと,そこだけはよく覚えています.
<外国では使えるのに>
あるときテレビで,患者さんが薬の話をしていたんです.当時,ジェムザールという膵臓癌の薬はまだ日本では使えなかったのですが,アメリカでは承認されていて,そのことで患者さんが道端で署名を集めて,自分にも使えるようにしたいと活動されていたんですね.
その患者さんは,効果も副作用もわかっていて,その上で自分も使いたいとお願いしている.その状況にはすごく違和感がありました.
―――違和感ですか.
そうですね.効果や副作用を患者さんもわかっていて,それでも使いたいと言っているのに,なぜ使えないんだろうと.外国では使えるという状況も,おかしいというか,どうしてそうなんだろうというのがありました.それも大学3年目くらいのことでした.
それで,3年目以降は,USMLE(米国医師国家試験)やECFMG(米国で臨床留学する場合の研修許可書)を取るための勉強を始めました.
―――ドラッグ・ラグに対する違和感.
出身は東北大学なんですが,研修病院を決めるとき,関連病院には見学に行きませんでした.代わりに,千葉の鴨川に亀田総合病院というところがあり,ここだな,と思って研修先に決めました.海外から帰ってきた先生や外国の先生を招いてティーチングをやっていることで有名でした.
<もっと自分でがんのことをやりたい>
当時の初期研修は,循環器なり麻酔なり,いろんな部門を回るという形式でした.当然,回る部門によって,循環器がおもしろいと思ったり,小児の病気をどうにかするのは大事だなと思ったり,それぞれに面白みがありました.2年間ローテーションする中で,悩まなかったわけではないんですが,回った消化器に,がんの患者さんが多かったんです.
胃カメラや大腸カメラをすると,がんそのものが見えるんですよね.ときには出血をしていたりする.処置をしたり治療をしたりすると,それが目に見えて小さくなっていくというのがわかりやすかったです.内視鏡をやるのも好きでしたから,2年目に消化器をローテーションしたあと,3年目,後期研修でも消化器を選びました.
―――3年目も亀田で.
亀田で1年,2年とローテーションして,各科ともおもしろいと思いながら,やっぱりがんをやろうかなと思ったところで,さて,アメリカに行こうかどうしようか,と考えました.
やはり,アメリカのほうがドラッグ・ラグがない.向こうのほうが優れているし,進んでいる.だからUSMLEも取ったわけです.でも,結論からいうと,行かなかったんですよね.
―――めぐり合わせ的なものでしょうか.
海外から帰ってきた方々と何人かコミュニケーションを取ったんですが,この人みたいになりたいなという方と出会えなかったんですよね.仕事自体は私の目指す方向だったりしても,スタンスというか,すごくスペシャリティなんだけど,全人的ではないというか.
患者さんを診ずにカルテを見ている,みたいな気がしました.
お会いできた人数は限られています.ただ,自分が見た限りで,この人みたいになりたいからアメリカに行きたいとは思わなかったんですね.
それと,初期研修を終えて,いよいよがんの治療や消化器をやっていこうというタイミングでアメリカに行くとなると,また初期研修からスタートになってしまいます.ほかの内科をまた回るというよりは,3年目からは自分でもっとがんのことをやろう,と思って,結局海外には行きませんでした.
<本に書いてあることと全然違うな>
―――学生時代に考えていたことと,研修をはじめてからの印象とで,ギャップのようなものはありましたか.
そうですね……僕は大学の病院実習って,じつはあんまり得意ではなかったんですよね.見学,っていうスタンスが嫌いで.
行って見ているだけというのがすごく嫌で,けっこうサボりました.その間,本で勉強をしたりしていました.USMLEの勉強をしたり,いわゆる内科学の本で勉強したり,英語や日本語で文字として読んで,背景だとか生理学だとかいろんな勉強をするわけです.
でも,いざ研修医になってみて思ったことは,本に書いてあることと実際の患者さんとがぜんぜん違うな,ということでした.
教科書ではこの薬をやりましょうと書いてあっても,実際には,どの薬をどの溶液に溶かして何日やるかとか,栄養の点滴はどうするかとか,他にも支持療法があったりとか,それを看護師さんにどう伝えてどうやってもらうかとか.
本に書いてある病気の流れと臨床現場とが,それはもう,ぜんぜん違うなっていうのが,一番大きいギャップでしたね.
なので,本を読むよりも,病棟にずっといて,患者さんから学んだほうがいいな,っていうのが,最初の研修医のころの印象です.
<会いたいです>
―――亀田という病院自体が,現場での経験をたくさん積むことができる病院ですね.
亀田には3年いました.いろんな科を経験させてくれる教育病院として有名で,内視鏡の数も全国の中でかなり多い方でしたから,そこに来る消化器内科の先生は,カメラなどの専門的な手技を学びたくて来られているような感じでした.
一方,がんの患者さんについては,今は腫瘍内科がありますけれど,当時はなかったんですね.ですから,各科が診ていました.消化器内科は胃がんや大腸がんを診て,患者さんもたくさんいました.ただ,化学療法を中心に診ている先生というのは特にいませんでした.カメラをやりながら,抗がん剤もみんなで分担してやっていたんですね.
3年目のとき,自分はそこをやりたかったので,「このがんだったらこうやって治療するんだ」といったことについて,サマリーを作ってみんなに配ったりしていました.
―――今でいう,電子カルテ上に抗がん剤のプロトコルを登録するみたいなことを,当時やられていた,ということでしょうか.
そうですね.そういうことをやって,みんなで勉強会をしたり,あとはデータベースを作ったり.患者さんから学ぶというのがやっぱり大事だなと思いましたので,自分の担当以外の患者さんの経過などもデータベースにまとめたりしていました.
当時は,もうずっと病院にいました.今では怒られますけれど,内視鏡室で寝泊まりして,1週間に1回だけ家に帰るような感じで.
―――そのまま亀田でしばらくお勤めに.
いえ,その後,青森県の三沢病院というところに行きました.
当時,亀田には腫瘍内科メインの先生がいなかったので,みんなで勉強しながらやっていましたが,あるとき青森から,三沢病院の院長であった坂田優先生がいらっしゃったんです.S-1やイリノテカンなど,今に至るまで使われている抗がん剤の開発に関わっていた先生なんです.その方が講演に来られたんですね.ちょうど,3年目の8月くらいのことでした.
講演の内容は,「臓器機能が低下している人に,抗がん剤をどうするか」という話でした.当時はそういったことに関する教科書がなかなかなかったですね.
―――いわゆる「さじ加減」というやつでしょうか.
そうですね.治療の選択肢としてはこれがありますよ,みたいな.レジメンはあったんですけれど,それが使えないとき,たとえば腎機能がもう透析寸前だとか,黄疸が出ているとか,そういった人びとにどう使っていくかという話を,坂田先生は延々とされたんです.
これをやりたいな,と思いました.その夜に懇親会があったんですが,その場では話せなかったので,翌日にホテルに押しかけまして.
―――え!
坂田先生の付き添いの人や,製薬企業の人がいたので,「会いたいです」と連絡してホテルに行ったんです.「先生の話がおもしろくて,勉強したいと思ったので教えてください」と.
―――3年目で.
3年目ですね.坂田先生には「じゃあおいで」と言われまして,4年目からはそこに行こうと.でも残り半年ありましたから,毎日坂田先生にメールをしていました.
<いろいろ教えてもらいながら,患者さんが良くなっていく>
「こういう胃がんの患者さんが来て,臓器機能がこうで,自分はこういう抗がん剤をやろうと思っていますが,どう思いますか?」みたいなメールです.すると,「いや,こっちの治療のほうがいいと思いますよ」という返事が来たりする.そんなメールを毎日していました.たいてい,自分がこうした方がいいと思っているのとは違う返事が帰ってきていました.
半年間で百六十何通のメールをいただきました.今でも大事に取ってあります.
―――半年って百八十日しかないですよね(笑).
本当に毎日していました.「年末年始はメール見られないからメールしてくるな」って言われたのも覚えています(笑).そうやって,いろいろと教えてもらいながら,目の前の人が良くなったりしていったんですよね.
責任感を持って目の前の患者さんを3年診ていると,もうちょっとこの人たちと一緒に治療をしていかなきゃな,とは思いながらも,でもやっぱり直に坂田先生に教えてもらったほうがいいなと.複雑な思いもありましたが,4年目からは青森に移動しました.
―――そのときの思いは,「複雑」だったんですね.
やっぱり,3年目でも主治医として,責任を持って患者さんを診始めていましたから.
<全体と,一人と>
―――当時,坂田先生から帰ってくるメールをご覧になって,自分との違いは何だと思われましたか.
経験なのかなと.「このがんなら,こういう薬でどうですか?」って聞いても,「いや,体調とか,その病状ならこっちの組み合わせもあるよ」みたいな.薬の選択肢なんて,今よりはるかに少なかったはずなんですけれど,「それがいいよ」と言われたことはかなり少なかったです.
―――今より抗がん剤の選択肢が少ないのに,それほど差が出るものなんですか.
種類は確かに少なかったんですけれど,そもそも,標準的な治療というものがうまく確立されていないというところもありました.たとえば,二つの薬を組み合わせるにしても,何パターンかのやり方があります.量にしてもです.
―――今は大規模な統計によって,標準治療とか推奨レジメンといったものをある程度教わることができるのかと思いますが,それでも,腫瘍内科医の方々を診ていると,やはりすごく細かな調整をされているなあと感じることはあります.
標準治療というのは,元気で臓器の機能がよく,他の併発症がない,抗がん剤を投与できる人というのが前提で決まっていきます.それは当時も今も一緒ですね.そして,実際の医療現場では,そこから逸脱する患者さんもたくさんいるんですよね.
さらには,患者さんのご希望とか様子とか,ご家族のサポートといったいろんな側面もふまえて,総合的に,という感じです.
やはり,本に書いてあることと実際の患者さんとは,文字から想像していたのとは全然違っていて,つらさにしても,薬が効いたときの喜びにしても,違うところはたくさんあるんですよね.難しいなと思いながらも,やる気がかき立てられたっていうところもあります.
―――臨床試験で,健康かつ若い人を中心に立てられたデータとの違いがあるんですね.
臨床試験は「全体」でしか見られないですよね.それはもちろん大事なことで,僕も講演ではそのような話もしますが,でも,中には一人ひとりの差もあります.
一方で,一人だけに囚われてしまうと,今度はそれが全体に反映されない.
この人がこうだったから,じゃあこれが全員に当てはまるかっていうと,そうはなりませんね.一人ひとりの違った反応を集合させての結果が大事になってきます.だから,両方大事なんですよね.
<抗がん剤や緩和医療っていうのはチームだ>
―――三沢病院に行かれてからはどうでしたか.
亀田のときもそうだったんですが,三沢にも見学せずに行ったんです.行き当たりばったりでした.三沢の印象は,病院がちっちゃい,ぼろいなと(笑).天井なんかすぐに手がついちゃいそうで,雨漏りもしそうな感じで,ここで大丈夫かなと思いました.でも,例えば,放射線とかCTといったものは最新のものがあって,「がんについては特に頑張る,しっかりやろう,小さい中でもやろう」としていたんですね.
そして,医者が少なかったです.本当に田舎.百何十床あったんですが,内科の医師は数人で,一人で三十人の入院患者を担当したり,外来も五十人,六十人.でも,そうなってくると,やっぱり看護師さんとか薬剤師さんとか,そういった方々との連携やチームというものがすごく大事になります.
坂田先生も講演で,「抗がん剤や緩和治療っていうのはチームだ」とおっしゃっていました.
亀田のときも人がたくさんいましたから,チーム的な感じはありましたが,勉強会とか委員会とか,そういう感じだったんですよね.でも三沢のときは,とにかくチームで分担して,その患者さんに対してやれることをやる.病院は古いし小さいって思いましたけれど,がんの治療については特化してやってるなってことは,最初からすごく思いました.
―――近隣の大学とか拠点の病院との関係はどんな感じだったんでしょうか.
大きい病院から出向と言いますか,関連病院として内科にやってきて,時間が経てば戻る,といった先生が多かったですよね.
院長の坂田先生や上の先生方はずっといる感じでしたが,僕くらいの年齢の先生は,来て少ししたら帰るみたいな,そういうところに,亀田っていう全然違う場所からやってくるというのは,すごく珍しいっていうかほぼいなくて,たぶん,珍しいやつっていう扱いでした(笑).
―――そういう病院の,腫瘍内科というのはどういう雰囲気だったんでしょうか.
患者さんは近隣の方が多かったですが,坂田先生が有名でしたので,いろんな病院で抗がん剤をやって,厳しくなった状況でやってくるという患者さんが多かったです.
そういう人に対して,外来で坂田先生が話すんですが,常に希望を話すんですね.当然,いろんなことをすでにやってこられていますので,なかなか厳しい状況なんですが,いろいろと工夫をしまして.そこで入院された患者さんを僕が担当する,みたいなことをたくさん繰り返しました.
―――当時はまだ,抗がん剤を使うとなったらほぼ入院しなければいけない時代ということで合っていますよね.
世間の認識はそうでした.でも,三沢では,できるだけ外来でやろう,と.看護師さんや薬剤師さんたちと,そういう体制をなんとかつくっていました.規模としては小さかったですが,入院と外来で,両方やっていましたね.
患者さんをたくさん診させてもらったんですが,当時の外来は電子カルテじゃなくて紙カルテでした.翌日抗がん剤をやりに来る患者さんの,外来のカルテが積み重なっているんですね.抗がん剤の人には赤いシールがついている.それを前の日の夜に,他の医者が担当する患者さんも含めて全部見ていました.
―――亀田のときと同じことを.
そうですね.経験を増やしたくて,それでデータをまとめたりしていました.FileMakerで,自分でフォーマットを作って.当然,匿名化をした上で,経過や画像とかを収集していました.その収集癖は親に似たのかなという感じですけれど(笑).
<薬が違うとこんなに違うんだ>
―――三沢には何年いらっしゃったんでしょうか.
3年ですね.3年亀田,3年三沢です.
具合が悪い人にもいろいろ考えて抗がん剤をするとか,さじ加減をするとか,そういうことを学んでいました.ただ,当時はやはり薬の種類が限られていたので,どう工夫しても,効果も経過も限られるなと思いました.
百何十人かの,具合が悪い方々のデータ,入院しなきゃ抗がん剤投与ができない方々のデータを,三沢にいた3年目の最後にまとめました.
当時,入院しなきゃいけない抗がん剤の患者さんに,抗がん剤をなんとか駆使して,具合が良くなって帰ってもらえる確率って,15%くらいだったんです.もちろん,やらなきゃゼロに近いので,良くなった人の記憶はあります.でも,まとめてみると15%.どう工夫してもこうなんだな,というのを実感していたころに,肺がんでイレッサが出ました.
やっぱり新しい薬が出ると違うなということを感じました.東北大学の緩和ケアの教授をしている,井上彰先生たちのグループが,それこそ入院しなければいけないような,酸素を吸ったりベッドに寝たりという方々にイレッサを投与した結果,具合が良くなる方が80%だったっていうペーパーをJCO(Journal of Clinical Oncology)に出したんですね.
当時,JCOを毎月,できるだけ読めるところは読んでいたんですが,それを見た瞬間にすごく感動しました.薬が変わると,こんなに良くなるんだ,と.こんなに具合が悪くても良くなって,家に帰ることができるんだ,と.自分たちがいくら工夫してやっても厳しいようながんが,薬の登場でこんなに違うんだ,と.
JCOにはエディトリアルがついていて,編集者がLazarus responseと書いていました.イエス・キリストが,棺桶から蘇る,それくらいのことだと称していたんですね.
ちょうど消化器領域でも,当時,オキサリプラチンとかアバスチンといった,今でも大腸がんなどで使われる薬が出てきました.使える薬が他になくなった方に新しい薬を使うと良くなるということも経験していたので,薬を世の中に出すというのが大事なんだなというのはすごく思いました.
そうすると,臨床試験とか,治験ということになっていくんですけれど.
<2人しかいなくて>
三沢の坂田先生は有名な先生で,昔はそういった薬の開発にも関わられていたんですが,もう卒業に近い状況で,臨床試験をやるにしても,効果安全委員会とか,自分で主導されるという感じではなかったんです.三沢は小さめの病院でしたし,治験はどちらかというと,大学病院やがんセンターがやっていました.そういうこともやっていきたいなと思ったのが,三沢にいた3年目の,夏ぐらいでした.
ちょうどそのころ,ASCO(米国臨床腫瘍学会)で,愛知県がんセンターの室圭先生に会いまして,「うちは人も少ないし,臨床試験もやっているからおいでよ」と言われまして.
―――室先生が「人も少ないし」と.
当時,愛知県がんセンターと近畿大学に見学に行きました.どちらもいい病院で,がんの研究をやっていたんですけれど,愛知県がんセンターのほうは,室先生と,宇良敬先生の2人しかいなくて,患者さんをたくさん診ていたんですね.近代のほうがもうちょっと洗練されていて,教室みたいな感じで,しっかりメンバーも揃っていました.けれど,自分が三沢でやっていたのは,愛知のほうに近かった,というのもあったんですよ.それで愛知に行ったんです.
そこに4年間いました.三沢のときは比較的幅広く,いろんながんを診ていたのですが,室先生のところは,どちらかといえば消化器メインで,呼吸器や乳腺以外を診て.ただ,何のがんがやりたいから行ったというよりは,臨床試験とか治験に関わってみたいと思って行ったんです.
<そういうものもあるんだぞ>
―――愛知ではどうでしたか.
臨床試験グループに参加をして,いろんな臨床試験をつくっていくための議論をすること,新薬の承認を目指すような治験をやること,そして研究所との研究,その三つをやりました.患者さんを多く診るというのは並行してやっていましたけれど,臨床試験グループの中で,みんなで今の治療よりももっとこうやっていこう,みたいなことを考えていくのはすごく楽しかったです.
あと,研究所も比較的近かったんですよね.僕がお世話になっていたのは,疫学予防部の松尾恵太郎先生で,患者さんの血液の遺伝子とか,習慣,食生活などいろんなものとがんとの関係を調べているところでした.そういうことと抗がん剤の効果との関係を見てみよう,とか.
喫煙をしていると食道がんになりやすいというのはわかっていましたけれど,じゃあ,その喫煙は抗がん剤や放射線の効きにも関わるのか,とか,食べ物によってTS-1の効果が違うとか,そういうことをいろいろやっていました.
よく覚えているのは,当時参加した治験のひとつで,プラセボコントロールの試験があったんです.プラセボか,実薬か,みたいな.それを,「がんセンターでこんなことやっているんですけど」と,三沢の坂田先生に相談したことがありました.三沢ではなにかあれば,適応外でもとにかく頑張ってやっていたんです.そのマインドからすると,それ(一部の人がプラセボを割り当てられること)が本当に妥当かっていうのを受け入れられるまで,ちょっとハードルがあったんですよね.
でも,坂田先生には,「きちっと決まった治療がない患者さんに対しては,サポーティブをしながらのプラセボっていうのもあるんだぞ,それはそれとして,薬を出すのが使命の施設もあるんだぞ」と言われました.
ご自身の病院と,がんセンターとの違いというのも理解されていたからなんでしょうね.
そういう研究をやったり,論文を書いたりして,4年間,すごく楽しくて勉強になりました.でも,治験の一番最初から関わったり,それを牽引しているのがどこかっていうと,やはり日本の中では国立がんセンターが一番だってことになります.
当時もドラッグ・ラグの問題は,大学にいたころをあまり変わっていませんでした.そこをどうにかしようと思ってやっていたのが,今は名誉院長になった大津敦先生,現・院長の土井俊彦先生,それと僕の前任の科長である吉野孝之先生で,3人がそのあたりを牽引されていました.
厚労省の班会議などでご一緒することがあり,僕もそういうところに中心的に関わりたいなと思ったところ,大津先生に「ぜひ来い」と言われて,がんセンター東病院に来たのが13年前です.そこからもうずっとここです.
<その患者さんですね>
―――そこからの設楽先生のご業績は,業界では知らない人がいないくらいものすごいことになっているわけですが,最初に論文を書いた「きっかけ」のようなものはあったんでしょうか.
最初は……亀田にいたころ,ローテーションしていた小児科で,学会報告をしようとしたんですけれど,途中でやる気をなくしてやめてしまったんです.そのときは,患者さんを「症例」として客観的に書くのが嫌になっちゃったんですよね.
―――そのときはまだ書けなかったんですね.
その後,ある患者さんが吐血して,胃カメラをやっても潰瘍とかがなくて原因が見つからなかったことがありました.また吐血をしたので胃カメラをやってもやっぱり見つからない.どこから出血しているのかなと思ったときに,CTを見たら,大動脈瘤に対してステントを入れていた患者さんで,ステントのところと十二指腸とがくっついていたんです.そこが若干怪しいなと思って,何か起きているかもしれないということで心臓外科に相談したんですね.すると,「そんなところから消化管につながるわけないから」って言われたんですけれど,夕方にも吐血してショックになり,結果,亡くなってしまいました.
剖検をしたら,大動脈瘤の手術のところと十二指腸との間でfistulaを作っていて,穴が小さかったときはじわじわ出血していたのが,最後には大量出血して亡くなってしまったんだなとわかったんです.
その後,PubMedで症例報告を見ると,似たような症例がちゃんと報告されていました.その中で,最初にちょっと出血することをoccult bleedingと呼んでいたんです.
症例を院外に報告して,まれなことも含めてみんなで共有していくということがすごく大事なんだなと思いました.
この人のことはどうしても論文に書かなきゃいけないなと思って,それでようやく1個目の論文,症例報告を書きました.
―――「どうしても論文に書かなきゃいけないな」の気持ちを,先生に注入した師匠がいたんですか?
その患者さんですね.
―――なるほど.
それは確実にそうですね.その患者さんが最初です.
あと,出版の時期はちょっと前後するんですが,僕が3年目のときに最初に診た胃がんの方です.胃がんがあって,肝転移や黄疸があって,当直のときに外来に来たんです.
明らかにCTでたくさんの肝転移と胃壁の肥厚があるから,翌日カメラをやりましょうと言って,カメラをやったら胃がんがあり,そのまま入院になりました.坂田先生に電話して,「こういう方がいて,黄疸をドレナージして,抗がん剤をこれからやるんだけど,どうしたらいいですか?」って相談をしました.「じゃあこれとこれを組み合わせてやろう」となって,そうしたらすごくよく効いて.
僕が亀田を辞めるときまで,どんどんがんが小さくなって,最後,胃だけ手術したんですけれど,その方,治ったんですよ.
それで10年後に,その患者さんの娘さんの結婚式に,僕を呼んでいただいたんです.患者さんと奥さんの間に座らせていただいて.その方についても,症例報告に書きました.
三沢に行ってからも,副作用で苦労していた患者さんのこととか,毎月のように,症例報告を書きました.3年間で17本くらい書いたと思います.最後は先ほど言った,百何十例かのまとめですね.
―――すばらしいですね.
愛知に行ってからも,症例報告も書きました.4年間でちょうど40本論文を書きました.
今,ありがたいことにいろんなところでチャンスをいただいていますけれど,最初からそうだったわけではなくて,やはり最初の1例の患者さんからはじめてやってきたので,若い先生には,いろんなパターンの論文の書き方などを共有できるかなとは思っています.
<自分だけ名前が出ればいいわけではない>
―――自分で書き切る論文と,誰かに任せる論文の線引きはどのようにされていますか?
最近,自分が担当する中で一番多いのは,企業との治験です.第III相試験とか,メジャーなジャーナルで薬の承認につながるようなものですね.そういう機会の場合は,企業に論文のライターがいたりして,共同してやっているので,自分で一から書く機会は減っています.
一方で,例えば,僕が主導してやった第III相試験で良い結果が出なかったりすると,企業のほうは書くのをスタートする足がちょっと遅かったりしますよね.そういうときは,もう自分でぱっと書いちゃったりもします.
若い方にもよく言うんですが,臨床試験って,やる前に理由があるんですよね.それが背景で,やったことがメソッドで,結果はそのまま書いて,ディスカッションは最初に思ったこととの違いを書けばいい.それは本当にすぐできちゃいます.
企業とのはこのようにするとして,あとは院内とか共同研究ですね.
患者さんを百人,二百人まとめるとか,そういうのはもう,立場的に自分が前にということはありませんので,若い方にファーストオーサーとして主導してもらいます.各臓器に指導する先生がいますので,その先生がコレスポンティングオーサーで,僕は全体を見るだけです.ただ,論文を直したり,研究に口を出したりとかは好きなので,嫌に思われない程度にはやりますけどね.
僕は科長という立場ですから,今でも論文に名前が出る機会はありますが,そこで次に何を考えるかというと,自分がどうなるかよりも,自分の周りの人がどれだけいい仕事をして,いい経験やいい業績を積み重ねていくかによって自分が評価される状況だと思うんですね.自分だけ名前が出ればいいとは全く思っていません.
周りにいいチャンスを作ってこそ,科の長なのかなと思っています.
ちなみに,お気づきかと思いますが,僕は基礎研究をまったくやったことがないんですよね.細胞実験はやったことがないし,動物実験もやりませんでした.
でも,そういうことの必要性はわかっています.やらずに来たからこそ,共同研究をやるときに,そういうことをやっている人をすごくリスペクトしていると思います.論文を書いたり読んだりはしているので,内容としてはある程度わかるんですけれど,自分ではやっていない.だから,そういう人たちと一緒に話をしたり,仕事ができたりするのは,すごく楽しいです.
だったら,基礎研究はそういう人たち任せだとか,その人たちより自分が下なのかというと,そうも思っていなくて,臨床だから言えること,コメントできることもあると思うんですよね.やっていなかったからこその今もあるかなと思っています.
<もっと増やしたいんですけどね>
―――亀田時代に良くなって帰る方がだいたい15%だったとのことですが,今だとどれくらいなんでしょうか.
ざっくり言えば,4割くらいになっていると思います.半分くらいまではいかないかもしれません.
抗がん剤の効果をはかる際に,奏効割合というのを出します.サイズを図ってどれだけ小さくなるか.面積でいうと,半分くらいよりも小さくなれば効いたという判断で,ちょっとだけ縮んだら横ばい,大きくなったら増大,みたいな簡単な区分をします.10人に4人が半分以下になれば40%の奏効割合,といったように.これが,元気に帰れる人の割合と,かなり一致するんですね.
亀田のころの薬というのは,奏効割合を考慮しても15%くらいでした.今は薬がいろいろ増えて,治療のラインや種類によっても異なりますが,どんながんも4割くらいの方がかなり小さくなります.
―――20年でだいぶ進歩しましたね.
そうですね.まだまだなんですけれどね.あと,5年間ご存命できる方の割合を出すと,20年前はほとんどいませんでした.今は十数%くらいにはなっています.
僕はかなりの数の患者さんを診せてもらっていますが,胃がんで抗がん剤だけで治った人がどれくらいいるかというと,40人くらいはいると思います.もちろん,もっと増やしたいんですけどね.
―――ちょっと嫌な質問をしますが,がんセンターでの奏効割合ではなく,たとえば先生が研修されていたころの三沢病院のような施設の奏効率でも40%くらいなのでしょうか.それこそ,地方と中央の「ドラッグ・ラグ」みたいなものはどうなのかと…….
当院で入院して抗がん剤をやる方のデータというのは,結局あのころ三沢で入院していた方と似たような感じなんですよ.うちにやってくる若い先生も,「がんセンターで,こんなに具合が悪い方を診ているとは思わなかった」なんてことを言います.食べられないから入院する,といったような.そういった方たちに限定しても,15%から40%くらいには増えていますね.
<○○○○○○○○○○>
―――昔と今とで,がんに携わろうとする人の数は,変わっていますか?
僕が今いる場所は,勉強したいとか経験を積みたいと言って来てくださる方が多いので,一般的な傾向からはちょっとずれているかもしれませんが,減っているとは思わないですね.でも,もっと増えてほしいなという気持ちはあります.早期発見によって一部のがんが減ったりする一方で,増えているがんもありますし,がんで亡くなる方の数や割合というものも決して大きく変わっているわけではないですので.マンパワーという点で,臨床にしても研究にしても,まだまだ必要です.
自分が考えた治療が,目の前の患者さんに効いたらすごく嬉しいです.臨床試験で再現されて,それが発表できて,みんなにじゃあこれをやってみようと思ってもらえたら嬉しいです.
臨床をやって,それを世界に公表したりみんなと共有したり,新しい治療や研究をやって,それを公開したり,それぞれがつながっています.どれもが莫大なやりがい……というと変かもしれませんが,その積み重ねだと思います.
落ち込むようなことももちろんありますけれど.たとえば,この治療がいいと思ってもそれがうまくいかなかったり,治験やプラクティスの中でうまくいかなくて患者さんが落ち込んじゃえば自分も落ち込むわけなんですけれど.
落ち込んだり元気をもらったり,いろいろあったとしても,できるだけ気持ちをすーっと一定に保つことを心がけています.
もちろん,患者さんが喜んでくれてよかったとか,それくらいはあります.でも,患者さんが落ち込んだときに自分も落ち込んじゃったら,患者さんを元気にできないので.
そこは客観的に見て,でも次はこうだからさ,とか.
臨床試験でうまくいかないときも落ち込むんですけれど.第III相試験がうまくいかないときは,よくネガティブ試験とか,客観的にディスアポインティングだとか言われますが,僕はできるだけそう思わないようにしています.
自分が考えて当時ベストだと思って,これがいいかもしれないと思って,倫理審査とかいろいろ通って,患者さんにも同意を取ってやっていただいて,結果がうまくいかなかったとして,それをすごいがっかりだ,だめだった,と思うと,患者さんに申し訳ない気がするんですよね.それはもう,ベストだと思ってやったことだから,それをやってこれがわかったんだったら,また次につなげようと.
できるだけそういう精神を保つようにはしています.
―――自分を高め続けるんだけれども一喜一憂しない,みたいな.
必ず,憂の方もありますのでね.でも,患者さんと一緒に落ち込んだりしていると,維持するのも難しい.
<来し方と行く末>
―――医学生や研修医たちがキャリアを積んでいく上で,どういう病院で研修するといい,みたいなアドバイスはありますか?
僕もいろいろなところでやってきたのですが,どこが良くてどこが劣っていたというのはなかったと思うんですよね.その場その場でやれることをやって,そこの中でのチームがあって,今ここでできること,たとえば三沢だったら多くの患者さんを診て,自分が最初から携わってお亡くなりになるまで診るというのをやってきた.
やっぱり,比較はできないですね.全部があったからこそ,今自分がこうなっているというのを強く思います.
ですので,若い先生にあえて言うとすれば,どの選択肢があったとしても,どれをとっても間違いっていうのはないんだということでしょうか.
それぞれに間違いはなくて,ただ,違いがあるだけなんです.そこで勉強したことを,こうやりたいなと思えば,また次につなげていけばいい.
―――今の設楽先生にとっての「次」は何でしょうか.
現実的には今やっていることの延長,なんですが(笑).もし自分がこの先,対外的に評価していただけるのだとしたら,新薬の開発にしても,世界での臨床試験にしても,もっと日本が主導してアピールできるようになっていったらいいなと思いますね.
そして,目の前のこと,やっていることを積み重ねながら,若い人で自分と同じように,あるいは自分を超えて,この領域で活躍してくれる人を増やしたいと思います.
それと……新しい治療法として,たとえば遺伝子治療や細胞療法などが,がん患者さんをさらに良くして,それががんじゃない医療にもつながっていくといいかな,みたいなことも,考えています.