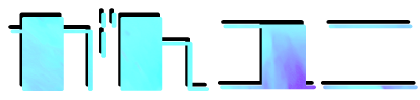2|18
ここから3か月の間に、CPCという会議を3回やることになった。それぞれ、剖検、すなわち病理解剖の結果を報告する。
ひとりはがん。ふたりはがんではない病気で、亡くなった。
病理解剖は、主治医や患者が病と歩むにあたってなにか「解せないこと」があったときに施行される。病名がつかなかったとか。治療がまったく効かなかったとか。なぜこんな結末を迎えたのかと患者もその家族も医者もみんなで首をひねっているようなケース。
そこに病理解剖という奥の手を加えて、すべてが白日のもとにさらされるかというと、そんなに甘くはない。でも、たまに、生前では気づくことができなかったであろう考え方にたどり着くこともある。
たまに、だ。いつもではない。
ただ今回CPCに持っていく症例は、3例とも、「解剖をしなければわからなかった。解剖をしたからわかった」というものだ。
解剖をしたからこそ解けた謎を、主治医チームのスタッフや研修医たちの前で提示し、病理解剖の結果をふまえて報告する。
解剖をして何かがわかったからなんだというんだ、とっくに手遅れじゃないか、と考える人もいる。
たしかに患者の死をひっくりかえすことはできない。
でも、詳しくは書けないし書く気もないのだけれど、この3名の患者の生と死を丁寧に解析することで、たくさんの人がこれからぶち当たるであろう困難への「対策」をつくれる。世界のどこかで似たような困難が起こったときに、私たちの患者の経験を活かすことができる。
それは手遅れではない。だからやる価値がある。
……でも、患者の死そのものをひっくりかえせるわけではない。まあ、なんというか、全開の笑顔で取り組むような仕事ではないと思う。
「なにがモチベーションなんだ」と問われることがある。「どうして患者を治せるわけでもない仕事につくんだ」、「治療しない医者なんておもしろいのか」、「患者から感謝されない仕事はつらくないのか」。
多様性の世の中と誰もがいうが、病理医の多様さはふしぎがられることのほうが多い。
病気をしらべ、名付け、分類をし、手遅れの解析。たしかにへんな仕事だ。
でもなあ。
「死んだらそれまで」の価値観ばかりで生きていたらしんどいだろう。
主治医や患者はそれでもいいけれど、どこかには、「死んでもまだ先がある」という姿勢でいる関係者がひとりくらいいてもいいんじゃないかと思うがな。