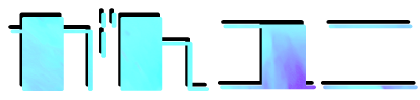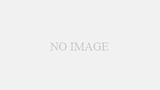3|2
若い病理医が、オンライン勉強会に出すスライドのチェックをする。文字少なめ、組織病理画像多めで、文字はメイリオで自己肯定感の高い印象。提示された写真からは、なるほど、このような所見に目配りしているというのは本質的な病理医としてのセンスがいいなと思った。
ただ、考察が足りていない気がした。
少ない染色。少ない免疫組織化学。そこそこ関係があるがドンピシャとはいえない参考文献。それっぽいが何も語っていない概念図。いずれも、今回の症例のふしぎさを解き明かすには、あまり役立っていないように感じた。
本当にこの病変に興味を持ったなら、病理医として、やれること、考えられることはまだある。それは「優秀なら気づく、経験が足りないと気づかない」みたいな話ではなくて、どんな病理医であっても、一晩じっくり標本と向き合えばおそらく普通に展開されるであろう「手さばき」のあれこれ、それが足りていない。やり尽くしていない。
はっきり言えば、中途のところで「まあこれくらいでいいや」とやってしまっているのではないか、と感じた。
その足りなさ、というか、のめりこみの浅さのようなものを、どうやって指摘したらいいか。あるいは指摘する必要もないのかもしれなかった。しかしまあ、べつに、他施設の、さほど世話になったこともない若い病理医に、このタイミングでキレられたり呆れられたり逃げられたりしたところで、別にどうでもいいかな、という気持ちもあった。一晩考えて、メールをした。
●正直、この内容だと、聞いた人もどう考えてよいのかわからないのでは……と思います。「珍しさを目合わせする」というのも研究会の目的として立派に許されるだろう、というお立場ならば今のままでも結構ですが、個人的には、まだやれることがあるのではないかと感じます。
●前提として、本例のような病態は、私もこれまで1,2例経験したことがあります。そのときの私もどうしていいのかわからずペンディングにしてしまいました。つまり、いまだにこれぞというお答えは持ち合わせていないですし、偉そうに言っても結局私もわかってはいないのですが、その点はご了承ください。
●本例ではPASしか提示されていませんが、ジアスターゼ抵抗性であることは確認されていますか? Alcian blueやムチカルミンだとどうでしょうか。MUC2, MUC5ACなどの発現はいかがですか? E-cadherinやβ-cateninなどで細胞膜を観察すると、この「粘液のようななにか」は、細胞のどの部分に収まっているのでしょうか? いわゆるdystrophic goblet cellと考えてよいのでしょうか? 核が多すぎませんか(内腔側にあれだけ核があるのにさらに粘液(?)の中に核があるというのはいったい?)? 粘液(?)の中に核がある形状がこんぺいとうのようで、粘液で押し付けられているという感じがないのですが、これは通常の大腸のgoblet cellとはちょっと違うようにも思いませんか? 粘液(?)が基底側にばかり存在し、側方へのずれがあまりに少なく整然と並んでいることに、違和を感じませんか? Ki-67 labeling indexはどのようになっていますか? Cleaved caspase 3などのアポトーシスマーカーを染めるとどうなるのでしょうか? じつは神経内分泌方向への分化があったりしないでしょうか?
●拝見したPDFには、「印環細胞みたい」、「淡明な細胞質を有する細胞」などと、随時記載していただきました。○○先生ご自身も最終的には印環細胞ではないと書かれているので、プレゼン内でのストーリーなのかもしれませんが、少なくとも「印環細胞みたい」という評価はH&Eの核所見の時点でなにか違うなと感じます。その上で、淡明な細胞質というならば、糖由来なのか粘液由来なのかをもう少し調べてみてもよいのかなと思いました。粘液だとしたら/粘液じゃないとしても、可能ならばそのさらに一歩先(たとえばひとつの細胞の中の粘液が基底側にあるのか、それとも内腔側とは異なる細胞が外縁に別個に分布しているのか)まで議論を進めたいですよね。
●ひとつの細胞の基底側に粘液(?)が整然とならぶというのは、いわゆるdystrophic goblet cellとしては「きれいすぎる」印象があります。個人的にはこのような分布はadenoma/carcinomaとNETがcollision/coexistするときのパターンに似ていると思います(今までもうっすらそう考えていたのですが、今回はきれいな症例のためか、今までよりもその発想がやや強まりました)。「だから神経内分泌マーカーも染めてみろ」とはいいませんが……今、書いていて思いついたのですけれど……NETにもclear cell variantというのがありますよね。INSM1くらい染めてみてもバチは当たらないかもと思います。なお、これがNETとは無関係だとしても(確率は高いですが)、たとえば、内腔の核と明るい細胞の核とはそれぞれ別の細胞由来だったりはしないでしょうか。そういった組織学的な「さぐり」がもっとあってもよいのかなと思います。p53の染色態度(うすさ、heterogeneity)が、内腔側の細胞と違うとか違わないとかが、ヒントにならないかな、とか……。結論が出ないにしても、組織病理でこれくらいは探れるという姿勢を出しておいたほうが、聴衆にとっても勉強になるでしょう。
●Histopathologyの論文について、Figure 1K, 1Lはたしかに本例と少し似ています。しかし、該当領域に関して引用している文献3つ(63, 64, 65)は、いずれも今回の○○先生の症例(もしくはFig 1K, 1L)とは異なる組織像です。よくあるsquamoid moruleや粘膜固有層内の骨化などについて語られているのでおもしろい論文ではありますが……。なお、Figure 4のシェーマは「わかった気になるシェーマ」というやつで、Reviewの格調を高めるために導入されていますけれども、そのじつ、本例の不思議さをなにも説明できてはいません。つまりこのHistopathologyの論文を紹介して終えるという流れは、本例のまとめとしてはさほど鋭くはないように思います。とはいえほかにいい論文も(今のところ)見つかりません。
●Greensonの「赤本」の、551ページの右下の、IBD-associated neoplasiaにみられるdystrophic goblet cellsと、本例の形態がほんとうに似ているかどうか。そこを形態を見ながら考える、くらいのことはできる症例だと思います。
●以上、昨晩からずっと考えていてまとまりもなくて恐縮なのですが、せっかくのいい症例なのでがっちり検討して考えて、その過程を○○○○○○○○でプラクティカルに提示する、というのはいかがですか、というご提案です。どうぞよろしくお願い申し上げます。
市原 拝復