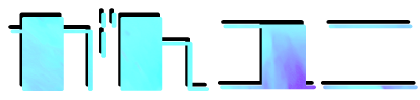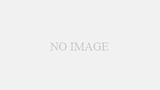11|17
気質がオタクなので細かめに仕事をする。主治医からの依頼は「これはがんですか? がんじゃないものですか?」、つまりは悪性か良性かを決めてくれ、ということなのだけれど、たとえばこれが悪性、つまりがんだとわかったとして、そこで話をおしまいにはしない。
がんなら、どういう性質を持ったがんなのか、どれくらい進行していそうかを調べる。どのようなタイプかまで見極める。治療方針にかかわるような「分類」は大事だ。たとえば、腺癌と扁平上皮癌とでは、使うべき抗がん剤が違ったりするので、同じがんという言葉でひとからげにするのではなく、ちゃんと仕分けておかないといけない。
ここまでは、普通の病理医だったら誰でもやる。ただこの先までやるかどうかは人による。
たとえば腺癌だとして、それが「どういう腺癌なのか」を、際限なく探っていく。時間がかかるし、お金もかかる。治療方針に関係するような検査はやっておいたほうがいいけれど、治療方針を左右しないような細かい分類を突き詰めるなら、それはもう「その患者のため」とは言えないわけだから、患者からお金をとるわけにはいかない。するとこの検索過程において、病院は「赤字」になる。
病院にも収支があり経営がある。病理医の個人的な興味と追求によって、病院を傾けてしまっては申し訳ない。
じゃあそれ以上の分類はしないかというと、それはどうも、病理医としての心意気に傷がつくような気持ちになる。
「このがんが結局なんなのかに、とことん深入りしてみたい」と感じるとき、取れる手段はだいたい三つだ。
(1)研究費を取って研究としてやる。
(2)自腹でやる。
(3)お金のかからない方法でやる。
一番いいのは(1)。でも、日常に遭遇するたくさんの症例ぜんぶに研究費を使っていくというのは、事実上むずかしい。
(2)は(私の場合)けっこうやりがちなのだけれど、あんまりいい方法ではない。そういうやりかたが定常化すると、自分はいいとしても家族や周りのスタッフ、そしていずれ私の後に入ってくる後輩たちが迷惑する。
やはり(3)だ。お金をかけずにとことん調べる方法が、ひとつある。それは……「細胞をじっくり見て考える」ことである。
見て考えることに金はかからない。細胞を長い時間見て考えると、思ったよりも新しい世界がひらけるような気がする。
ただその「じっくり」というのも、そうとうな「じっくり」でないと効果はない。1日、2日ではぜんぜん足りない。1週間で「あっ!」と気づくものがあればしめたものだ。わりと1年くらいは見る。患者の治療はとっくに終わっていたりする。それでも見る。ことあるごとに見る。他の症例と見比べるために10年かかるのは普通のことだ。そうやって、本当にじっくりコトコト見込んだプレパラートから、新たな分類の幕が上がることがまれにある。
なんのため、と言われてもわからない。「~~のため」と言えるような話題ではないのだと思う。ただ病理医たるもの、そうでないと、本当に難しい症例にはまったく太刀打ちできないんじゃないかな。強いて目的を述べるならば、「まともな病理医であるため」なのだと思う。