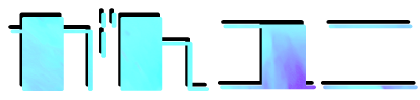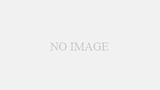13|22
ちかごろ、病理検査室でかなり流行っている業務というのがある。10年前にはほとんどなかった仕事だ。検体内に含まれる「がん細胞の割合」を調べるというものである。
胃カメラ、子宮鏡、気管支鏡……。さまざまな道具を使って、医者は患者の体の中から「がん細胞」を採取する。それががんであるかどうかを確定するためだ。しかしこの細胞、せっかく(患者に苦しい思いをしてもらいながら)取ったのだから、がん or not以外にもさまざまに検討するべきである。その一例が、「遺伝子検査」である。
がん細胞が持っている遺伝子のタイプによって、効く薬、効かない薬があるということを、人類はここ10年ちょっとではっきりと見出した。そこで、治療を始める前に、がん細胞のもつDNAやRNAなどをあらかじめ調べておくのである。これは、言ってみれば、そこにいるポケモンが、かぜ属性なのか、つち属性なのか、みず属性なのかによって、リザードンをぶつけるかカメックスをぶつけるかを選ぶ、みたいな話だ。相手の性質をきちんと把握すればするほど、対処がしやすい。
しかしここで問題がある。そもそも、がん細胞の採取のときには、がんだけをつまんで取ってくるということは難しい。小型のマジックハンドみたいなもので、がんのあるところをむしると、周りにある健常な細胞もある程度交じる。これが検査の障壁になる。
細胞を溶かしてDNAやRNAを抽出するとき、正常の細胞がたくさんあって、がん細胞がちょっとしかないと、調べるDNAのほとんどが「がんではないもの」になる。すると検査がうまくいかなくなるわけだ。相手のポケモンカードをまじまじ見ようと思ったらタロットカードやらトランプやら駅前で新入社員が配っている名刺やらがドサドサ混じっていてよくわからない、みたいな話。
そこで病理医は、プレパラートを見て、そこに含まれている細胞のうち、何%くらいががん細胞であるかを判断する。一般に、がん細胞の比率が30%を越えていれば、検査に支障はない。ただ20%を下回るとけっこう厳しくなる。
こんなのAIの判定装置でも作ればいいじゃねぇか、と思う。割合を考えるならば機会のほうが正確だろう。しかし、いくつかの病理AI開発に携わってみてわかるが、まあ、たぶん、無理だと思う。がんの種類が多すぎる。周りにあるがんではない細胞の種類も多すぎる。採取されるシチュエーションだってばらばらだ。オーダーメード感が強すぎて、商業的に使えるマシンにまで仕上げるのに無限に金がかかる。理論的にはいけるかもしれない。でも実践的に投入されないだろう。
この仕事がさあ……手間はかかるし……責任重大で……だって患者の治療の成否にかかわるわけでさ……そしてつまんないわけ……まあつまるつまんないで仕事してるわけじゃないからいいんだけど……。患者のためを思う心がないとふつうにがっくりするレベルの細かい業務である。病理医の仕事の中でも、もっとも紹介されてないんじゃないかな(つまんないから)。重要性はすっごい高いんだけどな。