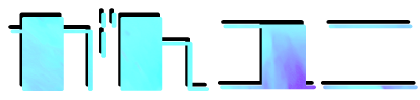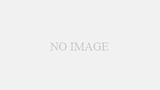14|31
近頃はいろんな人に、「がんとはどんな病気でしょうか」というのをたずね続けている。
そういうことをたくさんやると、ときおり、質問を投げ返されたりもする。
「病理医からみると、がんはどんな病気ですか。ほかの病気とどう違いますか」
うっ。
問うのは簡単だが答えるのは難しい。
そうだなあ。
病理医にとってのがんかあ。うーん。
「そうか、そうじゃないかが、わりと決められる病気」かなあ……。
がんのときは「がん細胞」が出現する。
がんでないときは、「がん細胞」は出ない。
何をあたりまえのことをトートロ言っておるのかと怒られるかもしれないが、これは決定的だ。
たとえば風邪を引いた人に「風邪細胞」は出ない。
心筋梗塞になってしまった人に「心筋梗塞細胞」は出ない。
糖尿病に「糖尿病細胞」は出ないし、骨折に「骨折細胞」は出ない。
ドラッグ中毒の人に「中毒細胞」は出ない。
しかしがんの人には「がん細胞」が出る。どこかには必ずある。それが検査でつかまえられるかどうかという問題はあるにしろ。
ほぼすべての病気は、もともと体の中にいらっしゃった(敬語)細胞の、数とか割合とかがいろいろ変わる。町の人口が増えたり減ったり、男女比や子ども・老人の割合が増えたり減ったりするように、構成が変化したり、ダイナミズムがおかしくなったりする。
しかしがんの場合はちょっと違う。がんは「それまではいなかった細胞」が出現して増える。
町に見慣れないチンピラがやってくる。ヤクザが闊歩する。ゾンビ。ゴジラ。
これががんの特殊性ではないかと思う。私たちは、「がんか、それ以外か」という「仕分けの気持ち」を、いつも心のどこかにひそかに抱えている。
「それって治療とか患者のつらさとか一切関係ないよね?」と、問い詰められるかもしれない。大正解である。検査・診断という側面においてがんは極めて特殊な病気であるが、逆にいえば、治療・維持管理という側面においてはがんはそこまで特殊ではない……のかも……しれない。
うーん。もっとインタビューしたいな。