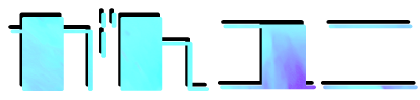0|1
猛烈に働いて夜中に帰宅。デスクの灯りを落とそうと立ち上がったらめまいがして、まあ、めまいくらいするだろうと思っていたが首ががちがちに凝っていて難儀する。帰宅、シャワー、めし、寝る、と済ませて翌朝、ぜんぜん治っていない。首ががちがちのままだ。ここまでやられるのは珍しいなと思う。ひさびさに湿布を出して首のつけねに2枚貼る。そのまま30分くらい忘れていたが、今、もうれつに首の後ろから有効成分がしみしみやってきていることを感じる。湿布とは手当てなのだなと感じる。誰かに労られ、手を当てられて撫でられる、のとはまあけっこう違うのだけれど、肌になにかが持続的に触れて何かを感じさせられ続けている状態というのは、それが「有効」成分なのかどうかとはあまり関係がなく、体の緊張をとるものだし、たぶんここにジクロフェナクナトリウムだとかロキソプロフェンナトリウムだとかが一切含まれていなくても、私はこの「当てられている感覚」だけで、少し癒やされるのではないかと思う。まして、それが、家族や医療従事者の手であれば、どれほど効果的だろうかと、世の中でとっくに消費し尽くされている肌への施しに対して今更ながら感謝する。高齢者の中に、もはや何がどこに聞いているのかわからないくらい湿布を貼りまくっている人というのが昔はいた(銭湯などでもたまに見かけたものだ)。あれも、おそらく、セルフ手当てだったのだろうな、ということを考える。