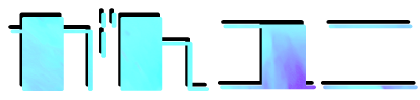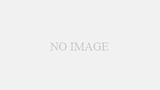6|4
毎週木曜日の朝7時半から8時半まではオンラインで勉強会をやっている。首都圏、関西、九州までの内視鏡医が集まって、朝から食道・胃・十二指腸・大腸の症例を、1日3例のペースで提示してみんなで写真を「読む」。腫瘍なのか非腫瘍なのか。腫瘍だとしたらどういう腫瘍なのか。どれくらい広がっているのか。どれくらい深くまで入り込んでいるのか。白色光内視鏡。インジゴカルミン散布像。NBI拡大内視鏡。酢酸、クリスタルバイオレット、ときに超拡大内視鏡まで……。
1時間で3例ということは、1例20分だ。だいたい15分でみんなが読影をして、私が残り5分で病理の解説をする。切除されてきた検体の肉眼像・組織像(プレパラート像)を説明しながら、内視鏡で病変をみたときの様相が「なぜそう見えたのか」を解説していく。
この勉強会は誰のためかというともちろん内視鏡医のためだ。内視鏡医は、カメラの先にあるイメージをどう解釈してどう治療に持っていくかというスキルを磨く。そして我々病理医の役にも立つ。やはり臨床の医師がどう見てどう考えたものをどう取ってきたのかをたくさん聞くほうが、病理診断をする上でも論旨がしっかりしやすいし、細胞をみるときの手続きにも切れ味が増す。
そして内視鏡医や病理医がこうして成長できることで、めぐりめぐって患者のためにもなるし社会のためにもなる……のだが……まあ、それはそうありたいものだが……。いくら勉強会をしたところで、患者ひとりの命をただちに救えるほどの成長は、なかなかできない。そこまでの効力はないような気がする。でも、患者のHPを10だけ余計に温存することはできるかもしれない。
休日、早朝、夜更け、いわゆる勤務時間外の勉強、できればもっと劇的に役に立ちたいものだ。科学者の記者会見でもあるまいが、メディア関係者から、「それって何か、社会の役に立つんですか」という言葉を、私達もわりと常に心のどこかに引っ掛けながら仕事をしている。申し訳ないが、そこまで、超・劇的に、何かの役に立つというほどではないんですよ。でもね。やらないよりはマシ、というかね。そうやって勉強会に延々と出続けた内視鏡医たちが今、学会のあちこちで活躍しているのを見て、即効性はないけれど、塵も積もればなんとやら、というやつかもしれないなあと思う日はある。