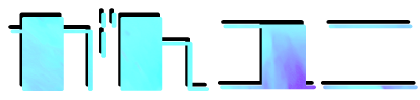4|6
勉強会に出る。今日の座長はあまりいい感じではない。言葉遣いがあやしい。「敬語をベースとしてときどきフランクに呼びかける」という口調、おそらくはよかれと思って用いているのだろうが、はっきり言って、「敬語を維持し続ける脳の筋肉がよわすぎて、ときおり礼儀の体幹が崩れている」ようにみえる。
礼儀・礼節をあまり気にしすぎる時代でもないとは思うけれど、おそらくこの座長は、患者や周囲の医療者に、ちょいちょいタメ口で話しかけているのだろうと思われた。ラポールが十分に築けている相手とならそれでもよいが、まだ関係を築いていない間柄で敬語がうまく使えない医者というのは、考えがあってそれをやっているというより、単純に思考の深度が浅く、惰性で、楽だから、習慣的に、それでも誰にも怒られないから、すこしスッとするから、偉ぶれるから、圧をかけられるから、ストレス解消になるから、敬語をほどいてしまっているのではないかと思う。
さらに言えば、そういう医者はよく、「忙しいときは考えられなくなることもあるよ。でも、いざというときはきちんと考えるよ」みたいなことを言う。いつまでたってもその「いざ」は来ない。
こういうタイプの人が座長をやると、あまりいい予感はしない。
案の定、勉強会はへんな方向に引っ張られていった。「自分がかなり迷った症例」を座長が自ら提示するのはいいとして、会に参加しているほかの病理医がそれにきちんと適切なコメントをつけ、座長よりも的確に診断にたどりつく方策を提案しているのに、それに向き合うことをせず、とにかく、「この症例は難しいからみなさんも私と同じように迷いますよね?」という方向に話題を引っ張っていく。居丈高だ。ハリボテである。さもしい。「こういう症例ありますよね。難しいよね。迷うよね。あるよね」みたいなことを、敬語をときおりほどきながら口にする。
座長は、その患者になかなか診断をつけられず、結局、かなりがんが進行した状態で手術になったそうだ。とはいえ、「座長が無能だったから患者に不利益が及んだ」とまでは言えない。実際、難しい症例ではある。写真を見る限り、その座長でなくても、特に序盤は病理診断するのが困難であったろう。ただし、少なくとも先ほど発言した病理医は、早い段階で違和感に気づいていた。となれば、座長はそこで、発言者のコメントを吟味し、自分を含めたほかの医者たちのさらなる思考をうながし、「優れた病理医の診断の手法をみんなで学び、明日にやってくるかもしれない同じ病気の患者に、今度はすばやく診断をできるようになろう」という学びの路を整えるべきであった。
私はウェビナーの画面を閉じながら思った。
「敬語がほどけてしまう程度の医者」は能力が低い。
偏見である。
しかし、なんだか、当分この偏見はぬぐえないだろう。