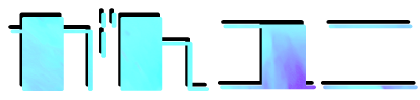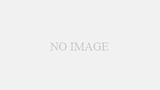6|12
ちょっと前の話。いわゆる「短報」と呼ばれる、論文の子どもみたいなものを投稿した。
普通の論文は、図(Figure)を数枚、文章は英語で数千語、参考文献はもりもりたくさん、フルボリュームで求められる。一方で短報というのは、Figureは1枚、文章は数百語、文献も5つ以内、みたいに少し短めに書く。そのぶんちょっと格調が落ちるのだけれど、「普通の論文にするにはちょっとだけありふれている/けれど論文として世に出すと喜ぶ人がいる」ような症例を報告するにはぴったりなのだ。
で、その、短報を書いた。Figureが1個しか用意できないから、がんばってデザインして、これぞという画像と病理を組み合わせたきれいな1枚を作る。文字数だって制限が強いから、必要最低限のことをしっかりまとめる。文献も選びに選んだ5編だけ。さあ! 通れ! と思って投稿。
結果はreject(掲載拒否)。残念だ。なにが悪かったのかなあ。査読のコメントを見て考える。査読者のひとりが、けっこう長く、理由を書いてくれている。それを読んで横転した。
Rejectの理由1.文章が短い。説明が足りない
Rejectの理由2.図が少ない。もっとのせろ。
Rejectの理由3.文献が足りない。もっとのせろ。
こいつ何いってんの? と目を疑う。レギュレーション(決め事)がわかっていないじゃないか。読んでいるうちにはたと気づいた。英語があまりに構造化されすぎている。文章にひっかかりがぜんぜんない。
こ、こいつ、AIで査読してやがるな。ピンときた。課金したChatGPTかGeminiかしらないが、とにかく、人間が考えて書いている文章じゃないんだ。だからやたらときれいな構成だけど根本的に間違った査読になっている。
そのことに編集部も気づいていないのだろう。それなりに名前の通った学会の公式雑誌なのに。悔しい。専門分野が私の本来のジャンルとちょっとずれているから査読に携わっているであろう人間の顔もあまり思い浮かばないけれど、ちきしょう、てきとうな査読しやがって……。
でもこれは自分への戒めともすべきだろう。人の真剣な仕事をAIにぶちこんで監査したり評価したりするときは本当に細心の注意を払わないと、まじで、ぜんっぜんピントのずれたことをやっちまう可能性があるってことだよな。