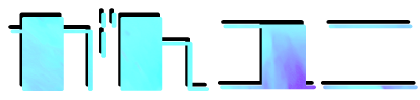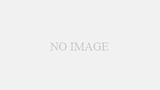18|16
とある患者の解剖をし、報告書を書いている。
私が1回の解剖にかける時間はだいたい2時間前後。純粋な作業時間でいうと平均1時間40分くらいだと思う。2時間越えることもあるが、3時間に達することはあまりない。ただ、これは、着替えをすっかりすませて解剖室に入り、患者の外表所見をとりながら主治医に経過や疑問点をたずね、「はじめます」と手を合わせて執刀をはじめてから、すっかり検索を終えて遺体をきれいに拭いて「ありがとうございました」と手を合わせて頭を下げるまでの時間である。
「解剖をしてほしい」と電話をもらってからかかっている時間はもっとずっと長い。各所への通達。総務課、病棟ナース、研修医への周知、自分の業務の引き継ぎ、時間外の連絡であれば必要な人員を揃えるためにも、人が揃うまで待つにも、時間をさらにかける。かけざるを得ない。「電話をもらってから自室で一息つくまで」を計測すれば、1回の解剖にかける時間が2時間とはとても言えない。肌感覚だがだいたい半日。それも、昼の半分(6時間)というのではなく、文字通り1日の半分、12時間くらいは「専心」する必要がある。
解剖が終わると、臓器をホルマリンに浸漬させて、1日待つ。昔はここで1週間待っていた。臓器を十分に固定するためだ。しかし、臓器をあまり長くホルマリンに漬けてしまうとRNAの検索がむずかしくなることが知られて以降、現代では、解剖の翌日にホルマリンから臓器を取り出して、「切り出し」を行うことが一般的だ(さまざまな理由で切り出しが2,3日後になることは許容される)。摘出した臓器をナイフで切って、写真を細かく撮り直し、顕微鏡で見るためのプレパラートを作成する部位を選ぶ。これにだいたい私は1時間半かける。病理医の平均的な所要時間よりもかなり早い。普通はたぶん3~4時間くらいかかる。
どうやってこんなに早くしているのか? 私が単に達人だということか? 自己顕示欲ブログか?
そうではない。
切り出しの前に1時間半くらいかけて、「解剖したときにとった所見、臓器重量」などを一気に記載してしまい、そこでイメージトレーニングをしておく。すると切り出しが格段に早くなる。それだけのことだ。つまり……実際には、ほかの人と同じ3時間を切り出しのために使っている。その場所が切り出し室であるか、自室であるかの違いだ。まあ、そんな、裏技などはないということだ。
プレパラートが出揃うまでに数日。そこからは顕微鏡で見る。考える。染色や免疫組織化学、in situ hybridization法などを追加する。考える。ここに、正味、2週間かける。飛び飛びで時間を費やしていく。ほかにも業務はあるから作業時間は断片的になる。今の私は、解剖を終えて平均約3週間で最初の報告書を出す。一般的な病理医はここで3か月~半年くらいかかる。
どうやってこれほどまでに早くしているのか? 私が猛烈な達人だということか? 自己顕示欲ブログか?
そうではない。
私は、病理解剖が終わってから何週間もずっと、ほかの仕事と同時並行で、解剖のことをずっとイメージトレーニングしている。すると検索や所見の記載が格段に早くなる。そして、この間、だいたい体重が約4キロ減るし、睡眠時間も平均で4時間くらい減る。本来、3か月~半年かけて使う集中力とかカロリーを短期間に一気に使い切っているだけである。つまり、まあ、裏技には裏技なりのリスクがつきまとう、それだけの話だ……。
この方式で解剖の報告書を仕上げるようになって5年くらい経つ。しかしそろそろ限界を感じている。第一に、体が壊れた。第二に、脳も壊れた。やめたほうがいいと思う。
さて、冗談はともかく、このスピードで解剖の報告書を仕上げるためには、もうひとつ、非常に大事な要件がある。私は、臨床医の全面的なバックアップを受けているのだ。解剖の報告書を病理医ひとりで書こうと思えばそれはもちろん半年以上かかる。でも、複数の視野、膨大な視点、人間ひとりが抱えることが不可能なレベルの知識を、「チーム」でなら運用できる。GPUを連結して計算速度を上げる、みたいな話だ。
ありがたいことに、私に解剖を依頼する臨床医は総じて熱心である。誤解をおそれずに言えば、ちょっと恐怖を覚えるレベルである。私が昼食をとっていようが、デスクで失神していようが、事前にアポなく病理にずかずか入ってきて、「先生、こないだの症例の参考文献、ここに置いときます!」「先生、例の血液データの解釈、ちょっと違う考えを持ってきました!」などと常に私を活性化してくれる。Gmailもやばい。LINEだけは死守したいがいつまで内緒にしていられるか自信がない。たくさんの脳がよってたかって私の解剖を仕上げていく。だから私は解剖の3週間後には報告書(第1報)を上げ、1か月後にはPowerPointファイルを作り込み、院内を巻き込んだカンファレンスで激論を戦わせて、その結果をもとに約2か月で第2報(最終報告)を届けることができる。
私の解剖をめぐる一連のスピードを知った他院のドクターはみな仰天する。臨床医は「そんな早く解剖の結果を出してくれるんですか? それはうらやましいなあ」と言う。病理医は「あんまりそれを外で言わないでください、誰もがそのスピードでやれると思われるとこちらも迷惑です」と言う。
前者のような臨床医に、「このスピードで出すためには解剖を依頼した臨床医がその後2週間くらいずっと、診療の合間に私のところに通い続ける必要があります」と言うと、黙ってうなずく。
後者の病理医に、「いえ、みんな真に受けないですから、大丈夫ですよ、だって私の言うことですから、みんなSNSの方便だと思っているでしょう」と言うと、黙ってうなずく。